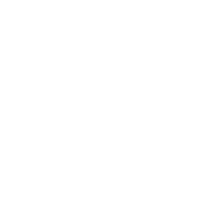第8話 岩城 良美「名前を呼んでくれないあの子」
病院の売店にはケーキが売られていなかった。
「ごめんなさい、アイスクリームしかないみたい……」
母さんは申し訳なさそうな顔で、バニラアイスを片手にガマ口財布を開く。花柄のパジャマから覗く手首は柳の枝のように細い。良美は首を横に振る。
「それは母さんが入院中に使うお金なんだから、自分のために使ってよ。入院中、何か急に必要になったら大変だから」
「必需品は看護師さんに立て替えてもらって、退院するときにまとめて払うから平気なの。バニラアイスでもいい? これが一番おいしそう」
バニラアイスの会計を済ませた母さんが笑った。青白い頬に優しそうな笑窪が浮かぶ。
「良美、お誕生日おめでとう。母さんが退院したら、とびっきりおいしいケーキ焼いてあげるからね」
「ありがとう、楽しみにしてる」
「大きいケーキに、ろうそくいっぱい立てようね!」
「いっぱいはいらないよ、十五本で十分だ!」
良美は売店の前で、誕生日ケーキの代わりにもらったバニラアイスの蓋を開けた。長い間売れ残っていたせいか、アイスクリームの表面には霜が降っている。銀色に光る霜を木べらですくってバニラアイスと一緒に口に含むと、冷蔵庫の味がした。
母さんが倒れたのは良美の誕生日の一週間前のことだ。せっせとパートで働いていたら、突然倒れてしまったのだ。働き者の母さんは仕事にやりがいを感じているらしくて、楽しそうに勤めていたけれど、無理をしすぎてしまったらしい。
毎日お見舞いに来ているせいか、病院の景色にもすっかりなれてしまった。点滴台を手に歩くおじさん、手すりに掴まるようにして廊下を通りすぎるおばさん。彼らが重たそうな両足を引きずって歩くたびスリッパが床をこする音が病院に染み渡る。
ここでバニラアイスなんか食べてていいのかな、と良美は木べらを甘噛みした。けれど目の前にいる母さんはにこにこ笑いながら、アイスを頬張る良美を見ている。
「母さん、どうかした?」
「良美が食べてるところを見てるだけ。母さんはそれが好きなの」
嬉しそうにしている母さんを見るのが、良美も好きだった。
「元気になったら母さんも一緒に食べよう」
「……う……うん」
にこにこしていた母は、にこにこしたまましゃがみこむ。
「具合悪い?」
「少し、貧血起こしちゃっただけ。大したことないから」
床に座り込んだ母さんは、片手をひらひらとかざして「大丈夫」とアピールした。偶然そばを通りがかった看護師さんが足を止める。
「あらあら。まだ、体力が戻らないうちは車椅子使っていいからね。きっと娘さんが来たから嬉しくなって、はしゃいじゃったんだろうね。ちょっと休みましょ」
看護師さんが素早く車椅子を持ってきて、母さんを座らせた。良美は車椅子を押す看護師さんの後ろについて歩く。
母さんのことはウチが守るから。海外で働く父さんとそう約束したけれど、こういう時、良美は母さんのそばにいることしかできない。
「少し血圧測るわね」
看護師さんは母さんを病室のベッドへ寝かせると、すぐに病室を出て行った。母さんは弱っている姿を良美に見せたくないようで、背を向けたまま動かない。
「母さん」
「大丈夫よ」
どんな言葉をかけたらいいか迷っていると、病室の外で物音がした。振り返ると、開けっ放しだったドアの入り口に毛糸玉が転がっている。毛糸の先はどこかにつながっているようだ。
廊下に出ると、車椅子の女の子と目があった。編棒と、毛糸を握っている。手元の糸を手繰り寄せようとすればするほど、床に落ちた毛糸玉はころころと転がり、遠くへ逃げていく。
良美は毛糸玉を拾うと、彼女に手渡した。
「何作ってるんだ?」
「長方形」
良美と年の近そうなその女の子は毛糸玉を乱暴に受け取ると、ふてぶてしく答えた。
「長方形だと?」
「編み物なんて地味な趣味、って馬鹿にしてるでしょ」
「馬鹿にするなんてとんでもない! たった一本の糸から何かを産み出すなんてすごいことじゃないか!」
「……ここじゃ、このくらいのことしかできないんだから。携帯も自由に使えないしテレビはばばあが独占してるし本なんかすぐ読み終わるし」
女の子が車椅子の方向を変え、良美の前から立ち去ろうとした時、血圧計をとってきた看護師さんと鉢合わせた。
「あら、ちひろちゃん。だいぶマフラーの形になってきたわね。編み物もいいけど、たまには歩く練習もしようね。その方が体のためになるから」
「わたしはもう歩けない」
ちひろは吐き捨てるようにそう言った。
「本当なら、車椅子卒業してもいいはずなのに。もう歩けるはずよ?」
「車椅子が好きなの。もう歩くのは嫌って言ってるでしょ」
「な、なんでだよ」
ちひろは、鬱陶しそうに良美の方を睨む。
「嫌いになるのに理由なんかいる? やりたくない。それだけ」
「そんな風に決めるのはまだ早いんじゃないのか?」
「早いも遅いもない。もう決めたの。わたしは絶対に二度と歩かない」
「歩けるようにがんばろう、ウチも応援するぞ!」
「それよりあなたはお母さんの心配したら? それから、アイスクリーム溢れてる」
「なっ…! 不覚!」
カップの容器からクリーム色の液体が伝い、床に点々と染みを残していた。良美はまごつきながら、片手でカバンに入れているはずのティッシュを漁る。
「これ使っていいよ」
ちひろは、編みかけのマフラーを、アイスクリームで汚れた床に投げた。甘ったるいバニラアイスを吸い込んだマフラーは茶色く汚れ、雑巾のように汚れていく。
良美が戸惑っていると、看護師さんが彼女に声をかけた。
「ちひろちゃん、あとで病室にプリン持っていくからね。誕生日のお祝いよ」
「スーパーで売ってるまずいプリンならいらないから新しい携帯電話が欲しい」
「今日が誕生日なのか?」
「昨日が誕生日だったの」
「おお! ウチと一日違いだな!」
「それがどうしたの」
「誕生日おめでとう!」
「こんなところで祝われても別に。お祝いなら、退院する時にして欲しいよ」
ちひろは車椅子に両手をかけると、母さんの隣の病室に消えていった。良美は床に落ちた編みかけのマフラーを拾う。ところどころべたついていて、指先に不快感が残る。けれど毛糸からは、病院の消毒液とは違った優しい花のにおいがした。
◇
父さんは、今アフリカにいるらしい。
真っ暗な家に帰ると、父さんから来ていた電話をかけ直した。
「誕生日おめでとう! お前と一緒に食べるつもりで、父さんも今夜はケーキ食べるぞ! ダイエット中だけどな!」
テレビ電話のモニターに、大きなホールケーキを持った父さんの姿が映る。そばには肌や目の色が違う外国の人たちがいて、父さんと一緒に盛り上がりながら良美の誕生日を祝ってくれているようだった。
「そのケーキに乗ってる果物はなんだ!?」
「これはこっちで採れるフルーツで、えっとーなんていったっけな……」
父さんの友達がケーキにろうそくを立てている。会ったことも話したこともない外国の人たちにまでおめでとうを言われるのがおかしくて、良美は「にぎやかな誕生日だな……」と小さく笑った。
父さんは「弱い立場の人たちを応援すること」に人生を捧げているらしい。良美が幼い頃から、まだインフラの整っていない発展途上国に向かい、仕事環境や生活状況が良くなるよう手助けをしてきた。良美には、そんな父さんの姿がテレビに出てくる正義のヒーローのようにきらきらして見えた。父さんはキックやパンチで悪を倒せるほど強くはないけれど、輝きだけならヒーローにも負けない。
「ところで、母さんは大丈夫か?」
「先生や看護師さんがずっと見てくれてるし、何かあったらウチがすぐ駆けつけるから父さんは心配するな!」
「そうか、お前がそういうなら安心だ!」
家を留守にすることが多い父さんに代わって、日本に残された母さんや、この家を守るのが良美の役目だった。もっと強くなって、いろんな人の背中を支えられるようになりたいと思う。
父さんとのテレビ電話を切ると、途端に部屋が暗くなったような気がした。どこからか、煮物のにおいが漂ってくる。良美は手早く具の少ないチャーハンを炒めると、テレビを見ながら一人で平らげた。
片付けを終え、ベッドに入ると時計の針をみつめる。午後十一時。もうすぐ自分の誕生日が終わる。そしたら今度は、あの子の誕生日だ。
ベッドの脇には、ちひろの作った編みかけのマフラーが置いてある。バニラアイスの汚れを取ろうと水に濡らしたら、毛糸が縮んでダメになってしまった。かといって、捨てるのも気が引ける。丁寧にたたんであるマフラーを見つめていた良美は、そっと寝返りを打ち枕に顔を埋めた。
◇
「また来たの。お母さんのことが大好きなのね」
病室の廊下で、車椅子に乗るちひろを見つけた。
「今日は、お前と話したくて」
「何?」
「マフラーって、編むの難しいのな。ウチもやってみたけど、気づいたら編み目が増えてて……」
紙袋から、台形になったマフラーを取り出す。ちひろが選んだのと同じ、白い毛糸で良美が編んだものだった。それを見たちひろは顔をしかめた。
「バカみたい。マフラーなんか編んでないで外で遊んできたら? あなた元気そうだし」
「お前にも元気をわけてやる!」
笑顔を振りまく良美を見て、ちひろは盛大なため息をつく。
「なんでこんなにわたしにかまうの? 大して知りもしないくせに」
「そうだな、確かにまだちひろのことよく知らないな。これから色々教えてくれよ」
「めんどくさい人……」
「そうだ、マフラーの編み方教えてくれないか? これ全然うまくいかないんだ」
「うわー、下手くそ。なんていうか、一言でいうとひどい」
車椅子に座ったまま、ちひろは良美を見下し、足を組んだ。
「足組めるんだな」
「組むくらい簡単よ」
「全然、お飾りの足じゃないんだな。歩かないなんて、宝の持ち腐れだぞ!」
ちひろはつまらなそうに鼻を鳴らすと、ポケットから携帯を取り出してゲームを始めた。目の前にいる良美には興味がないらしい。
「そのゲーム面白いのか?」
「今、イベント中で忙しいの。五千位以内に入らないといけないんだから」
ちひろが黙々と携帯をタップしていると、それを見かけた看護師さんが足を止めた。
「携帯電話は病室の中とナースステーションの中でしか使わないって約束でしょ? もう、約束破るなら没収ですよ!」
「嫌よ没収なんて絶対! これ、わたしのものなんだから!」
「もうすぐレクリエーションの時間だから、みんな集まってるわよ。ちひろちゃんもいかないと」
「ばばあとオセロとか絶対ヤダ」
「ばばあって言わないの! それから、携帯電話はナースステーションで預かります。ほら、携帯こっちに出しなさい」
叱られたちひろは、携帯を大事そうに握りしめたまま看護師さんに背を向けた。唇の両端を固く結ぶちひろにつられて、良美は拳を軽く握る。
「ごめんなさい、ウチここで携帯使っちゃいけないって知らなくて。次から気をつけます! それじゃ、ちひろと遊ぶ約束してるんでまた後ほど!」
はぁ、と呆れている看護師さんを横目に、良美は車椅子の背を押した。看護師さんを振り切るように、早足で廊下を駆けていく。
「速っ」
ちひろは、思いの外スピードが出ている車椅子の上でにやっと笑った。
患者はみんなレクリエーションルームに集まっているようで、廊下を歩いている人は誰もいない。
「もっと早く走って」
「大丈夫か?」
「スピード出してよ」
ちひろの要望に応えて、良美は人気のない病院の廊下を走った。車椅子の車輪が風をきる。短いちひろの髪がそよりとなびく。
はるか後ろで、看護師さんが「廊下は走らないでください!」と声を荒げた。それを聞いたちひろはくすくすと悪戯っぽい笑みをこぼしていた。
ちひろの指示で病院の庭に出ると、日陰に車椅子を止めた。柔らかい風が吹くと、木々の枝に咲く桜の花びらが揺れた。
「あー、すがすがしい。やっぱり病院の外は電波がいい」
ちひろは桜の花には見向きもせず、嬉々としてゲームの続きを始めた。
「そういえば、ちひろは年いくつなんだ?」
「こないだ十五になったところ」
「ウチと同い年だ! 誕生日も近いし、この出会いは運命かもしれないぞ!?」
「そう」
ちひろは涼しい顔でゲームを続ける。
「友達になろう! っていうかもう友達だ! だから、ウチはお前が歩けるようになるよう全力で応援する!」
「応援されても別に」
「ウチがついてるからな!」
「……もし次もまたくるなら、何か手土産を持ってきてよね」
任せろ! と良美は力強く叫んだ。病院からの帰り道、二本の足で歩きながら、「歩けるはずなのに歩きたくない」のはどんな気持ちなんだろうと思った。怖いから? 何が怖いんだろう。面倒くさいから? 車椅子の方が楽だから? 歩くのが辛いから? 何が辛いんだろう。何が何が、の堂々巡りに入って、良美は頭を抱える。
ただ、彼女をあのまま放っておくのは嫌だった。
「病院の売店で売ってるプリンよりおいしそうね」
母さんの見舞いに来たついでに、良美はちひろの病室を覗いた。お土産のプリンを見せると、ちひろの目の色が変わる。
ちひろが手を伸ばした瞬間、良美はプリンの箱を隠した。
「歩く練習がんばるなら、これやる!」
「えー、お見舞いにくれるんじゃないの?」
「ほら、歩こう!」
良美は、かろやかに歌いながら、ちひろの周りをくるくる回った。
「何!? 嫌がらせ!?」
「ぐぬっ……ウチは絶対あきらめないぞ! なんとしてもお前をやる気にさせてやるんだ〜っ!」
ちひろはしたり顔で笑う。
「やる気がない人をやる気にさせるのは無理よ!」
「自信満々に言うな!」
すると、同じ病室にいる少女が笑った。
「元気なお姉ちゃんだねー!」
少女も足が悪いようで、小さな子ども用の車椅子がベッドの脇に置いてある。ちひろは少女から顔を背けて、声をひそめた。
「他にも怪我してたり、病気の人たちはたくさんいるんだから、そういう子たちを応援しにいったらどう? わたしみたいなやる気ない人のところに行くより、やる気ある人を応援しに行く方がいいんじゃない?」
「どんなことでも、まずは一つずつ解決していかないといけないからな。まずはお前からだ」
「ああそう」
ちひろは面倒くさそうにあくびをして、その口元を手のひらで覆う。その手を見た良美は眉間にしわを寄せる。ちひろの手の甲に骨が浮き出ていた。彼女の手首はあんなに細かっただろうか。初めて会った時よりも、やつれているのかもしれない。
母さんの元気そうな顔を見た後に、ちひろの病室に顔を出すのが良美の日課になった。ちひろは嫌そうな顔をしながらも、新しい来客をしぶしぶ受け入れる。
ベッドに座っているちひろは、良美を見て二言つぶやいた。
「携帯。ナースステーション」
「没収されたのか?」
いつもより一層不機嫌そうに頷く。
「取り返してきて」
「う〜む。それは難しい相談だな」
「じゃあ帰ってよ。あなたに用はないから」
「そこのトランプ、ちひろの?」
「病院の」
「よぉ〜し! それで神経衰弱やろう! もしウチが勝ったら歩く練習すること」
「負けたら命令に従えってこと? なんか汚い」
ちひろは目を細めて、イヤらしいものを見るような顔で良美を見つめた。
「命令じゃない、大事なものを賭けた純然たる勝負だ! ウチが負けたら、お前の携帯を取り返してきてやる」
「まあいいわ。神経衰弱ね。それで携帯がかえってくるなら文句ないし」
良美はトランプのカードを切った。ベッドに備え付けられている台にトランプを並べていく。ちひろの歩行練習のためには絶対負けられない。良美は目を見開いてトランプを凝視する。
「……透視しようとしてる?」
「さすがにそれはできん!」
けだるそうなちひろ相手に、良美は全力で挑んだ。すべてのカードをめくり、ゲームを終えた良美は椅子から立ち上がった。
「ウチの勝ちだ! 約束は約束だぞ!」
そう叫んでから、ぐったりとベッドに寄りかかる。ちひろは呆れたようにため息をつく。
「わかってる。歩く練習ね。いいわよ。ちょっと付き合ってあげる」
そしてベッドから滑り降りるようにして車椅子に乗ると、良美に連れられてリハビリ室へ移動した。
リハビリ室には、マットレスや歩行マシーンなどが置いてあり、ちょっとしたジムのようだった。ちひろは車椅子で手すりの近くまで移動すると、ひざ掛けを外す。車椅子に守られていた足首は華奢で、リハビリ室にある巨大なマシーンの前では余計に弱々しげに見えた。
「無理はしなくていいからな」
「無理に誘ったくせに」
ちひろは前かがみになると、わずかに腰を浮かせた。
良美はちひろに手を伸ばす。ちひろはその手に目もくれない。裸足のまま、両足を床に下ろす。ぺたり、と乾いた音がなる。足の指がフローリングをつかむようにわずかに丸くなった。そして、彼女は何の力も借りず一人で立ち上がった。まっすぐに背筋を伸ばし、両手をあげて伸びをする。そしてその場でくるりと回る。紺色のパジャマの裾が膨らんだ。草原を走る少女となんら変わりない、元気そうな姿だった。
「これで満足?」
冷たい目で良美に笑いかけると、ちひろは車椅子に腰掛けた。
「そんな、簡単に立てるなら、なんで……」
呆然としている良美の前で、ちひろは激しく咳き込んだ。軽くえずくと、気分が悪いのか口元を手で押さえたまま顔を伏せる。
「吐きそう」
「トイレ行くか? 看護師さん呼んでくるよ」
ちひろは深いため息をつきながら頭をかきむしった。指の隙間に髪が絡み、はらりと抜け落ちる。
「ここで待ってろ、すぐ戻るから」
「もうこないで」
「え?」
「ちゃんと歩いたんだから、もういいでしょ。余計なことしないで。あなたは友達でも家族でもなんでもない。鬱陶しい赤の他人よ」
ひざ掛けで口元を抑えると、ちひろは片手で車椅子を操り、リハビリ室を出て行った。蛍光灯が煌々と光るリハビリ室に残された良美は、そばにある手すりを撫でた。自分が応援だと思っていたことは、ただの傍迷惑だったんだろうか。それどころか、ストレスや負担になっていたのかもしれないと思うと、ちひろに合わせる顔がなかった。
母さんの体は徐々に回復して、病院食も残さずきれいに食べているらしい。今日もまた母さんのお見舞いにきた良美は、ちひろの病室の前で立ち止まった。無理をさせてごめん、と謝りたかった。けれど「もうこないで」と言われた手前、強引に会いに行くのは気がひける。
「お母さん、もうじき退院できそうね。おめでとう」
部屋の前で立ち止まっていると、ちひろに声をかけられた。車椅子で院内を散歩していたらしい。
「ありがとう。えっと……こないだは悪かった」
「別に怒ってない」
病室に戻ろうとするちひろの車椅子の背を慌てて押した。ベッドに横になったちひろは、一息つくと良美の目を見据える。
「まだわたしのこと、応援してる? がんばれ、って思ってる?」
「思ってるよ。会いに来るな、って言われたけど、今でもお前のこと応援してる」
「じゃあ」
ちひろは、ふっと浅いため息をついた。
「じゃあ、あなたの元気な体をちょうだいよ」
良美は息を飲んだ。言葉が出なかった。
「本当にわたしのこと応援してるなら、ちょうだい」
良美が口を開くと、ちひろは小さく吹き出した。
「変な顔。これあげる。がらくただけど」
ちひろがベッドサイドにあった紙袋を突き出した。
「あ……ありがとう。開けてもいいか?」
「家に帰ってからにしたら?」
「また来るね」
「うん。それじゃ」
紙袋に入っていたのは、白いマフラーだった。編み目がガタガタで、異常なほど伸縮性が高い。端の方が台形になっているのは、良美が中途半端に編んだせいだろう。ちひろも編み物が得意というわけではないらしい。とてもファッションアイテムとして首に巻ける代物ではなかった。けれどそのマフラーを身につけると、自然と笑みがこぼれる。赤の他人じゃないだろ、とつぶやくと、良美はマフラーに顔を埋めた。
◇
母さんの退院が決まった日、良美は学校が終わるとすぐに病院に向かった。母さんはすでに退院の準備を済ませていて、大きなトランクには病院で使ったパジャマやマグカップ、歯ブラシなんかが綺麗にパッキングされていた。完璧に片付けられた病室をみて、良美はわなわなと震える。
「ウチが手伝えることが何もない……っ!!」
「大丈夫よ、わざわざ来てくれたのにありがとう」
「くっ、もう少し早くついていれば……!」
「いいのよ、母さんが入院してる間、良美一人で家事も全部やってたんでしょ? これからは母さんが毎日おいしいご飯作ってあげるからね!」
「期待してる! それじゃ……ちょっと隣の病室見に行ってくるよ」
「友達がいるんだものね。いってらっしゃい」
良美は意気揚々と病室へ向かった。先日もらったマフラーのお礼に、小さなケーキを買ってきたのだ。病院で食べた誕生日のプリンより、ずっとおいしいはずだ。
「おーい、ちひろ! 元気か?」
個室のカーテンを開けると、ベッドは空だった。ふっくらした枕には凹み一つない。病室を移ったのだろうか。病室と廊下の間を右往左往していると、看護師さんに声をかけられた。
「誰かお探しですか?」
「この部屋にいた女の子……ちひろは? どこ行ったんですか?」
「ああ、あの子なら、大学病院に移りましたよ。ここより設備が整ってるから」
「元気になって戻ってきますか?」
「ええ。きっと、大丈夫よ」
看護師さんは、軽く微笑むととすたすたと通り過ぎていく。病室の窓から冷たい風が吹き込んだ。桜の花びらが音もなく散る。
「ちひろ……」
ちひろがいなくなった病室の、白い壁が寒々しい。窓から舞い込んできた桜の花びらを拾った。もしウチが神様になれたら。散りかけの桜を満開にしたり、細い枝をにょきにょき伸ばしたりできるんだろうか。もしウチが神様になれたら。なれても、そんなことをするのはやっぱり怖い。じゃあ何ができるんだろう。そばにいること。話し相手になること。誰かのためにできることはその二つぐらいだと、自分の身の程なら嫌になる程わかっていたはずなのに。
(病院をうつるなら、一言くらい言ってくれよ)
良美は柔らかいまくらに、手のひらを落とした。折り目のついた新しいシーツが次の患者を待っている。
不安な気持ちを押し殺すように、ふっと息を吐く。
(いつか、元気になったちひろと一緒に、おいしいケーキが食べられたらいいな)
そう囁くと、ベッドに背を向けた。
「あ……」
その時、隣のベッドで寝ていた少女と目が合う。その膝の上にあるスケッチブックには、ケーキ屋さんやパン屋さんの絵が描いてあった。人間より大きなサイズのケーキたちが、ショーウィンドーから飛び出して花畑の上を飛んでいる絵だ。
「お菓子好きなのか」
「うん! でも、病院に売ってるケーキはあんまりおいしくないんだよ」
「じゃあこれ、よかったら食べろ。うまいぞ!」
「え? 本当に?」
ちひろに渡せなかったケーキの箱を渡すと、少女は頬を紅潮させた。
「それじゃ、ウチはそろそろ行かないと」
「お姉ちゃん」
少女に呼び止められて、良美は振り返った。
「ありがとう。すごく、うれしい」
ケーキの箱を開けた少女が、にっこりと笑う。
今、目の前にいるこの子が、少しでも前向きな気持ちになれたらいい。ちひろには会えなかったけれど。
瞼を抑えると、涙が静かに引いていく。ウチが寂しい顔をしてたら、誰かを応援することなんてできないじゃないか。
病室のカーテンが風でふくらみ、窓の外に見える小枝が揺れる。桜の花びらがひとひら迷い込んで、ちひろが寝ていたベッドの上へふわりと落ちた。