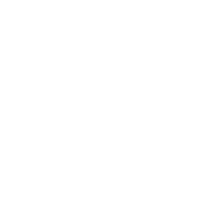第7話 鈴木 和香「sunlight」
タイムカプセルの中に野球ボールを隠したのを、未だにずっと後悔している。あの頃のお気に入りだった、くねくね曲がる鉛筆でも入れておけばよかったのに、和香が持ち出したのはお兄ちゃんの大事な野球ボールだった。
「おとなになるまで大切にしていたいものを持ってきてね」
小学校の先生にそう言われて、和香が真っ先に思い浮かべたのはお兄ちゃんの姿だった。和香のお兄ちゃんは野球少年団に入って以来、野球の話ばかりするようになった。
(おとなになるまで大切にしていたいもの、おとなになる前になくしてしまうかもしれない)
タイムカプセルを埋める前日、和香はお兄ちゃんの野球ボールを盗んだ。野球にお兄ちゃんを取られてしまうんじゃないかと不安で胸が押しつぶされそうだった。
せめてわたしがおとなになるまで、お兄ちゃんがそばにいてくれますように。そう祈りながら、タイムカプセルに土をかぶせた。
けれど、お気に入りの野球ボールをなくしたお兄ちゃんは、和香が中学生になった今でも野球を続けている。
「5番、セカンド、鈴木君。背番号4」
和香は立ち上がった。バットを持ったお兄ちゃんが打席に入る。「打て鈴木!」「ここで頼む!」とあちこちから応援の声がかかった。ざわつく球場の中で、和香は祈るように両手を合わせた。大きな舞台、集まる視線、その肩にのしかかるチームの期待。堂々と打席に仁王立ちする、背番号4番の二塁手。高い守備力を持つだけでなく、打撃にも強いスター候補選手だ。
(あそこにいるのは、私のお兄ちゃん)
「わー、あの人かっこいいね」
「鈴木君? わかるー! わたしも前から狙ってた! あの人絶対プロ野球行くし!」
「えーすごーい、かっこいいー」
お兄ちゃんの姿をみて女子たちが沸き立つ。和香は彼女らに冷たい視線を送る。
「……ここはアイドルのライブ会場じゃない……野球観戦する場所よ……」
和香のぼやきは派手な応援にかき消され、誰の耳にも届かない。
下唇をそっと噛む。お兄ちゃんの事を何も分かっていない女子たちの黄色い声援を聞くと、試合を放り出して一人で帰ってしまいたくなる。
お兄ちゃんのこと、応援してるわ。
それが和香の口癖だった。
お兄ちゃんは、ありがとう、と優しい笑みを浮かべる。
一生懸命応援するから……これからも、私だけのお兄ちゃんでいてね。
そう言うと、お兄ちゃんはいつも決まって、肉刺だらけの固い手で和香の頭を撫でてくれた。
昔はそんなお兄ちゃんから離れられず、毎日のように野球場に通っていたけれど、今では大事な試合のみ応援しにいくようにしている。お兄ちゃんが野球を頑張っている間、私は野球の研究を続けたい。そしてお兄ちゃんがもしもつまづいてしまった時に、的確なアドバイスができるような妹になりたいと思っている。
カン! と乾いた音がして、ボールが右中間へ飛んで行った。
お兄ちゃんがフルスイングした後、バットを捨てて一塁ベースを踏み、二塁まで走った。客席から大きな声援が飛ぶ。そばにいた女の子たちが「すごーい」と騒いだ。和香は腰を下ろした。
野球で活躍するようになってから、お兄ちゃんは和香だけのヒーローじゃなくなった。お兄ちゃんはチームの仲間にとって「頼れる男」で野球ファンにとっては「プロ入り期待の選手」、そして女子にとっての「憧れの人」だ。
お兄ちゃんの努力が認められていくほど、和香の中だけにあったお兄ちゃんの欠片がぼろぼろ表に引っ張り出されて遠い空に輝く星になる。和香は「私だけが知っていた」お兄ちゃんの成分をかき集めてもう一度自分の中に閉じ込めておきたい想いにかられながら、球場の影を見つめる。
お兄ちゃんを応援したい気持ち。私だけのお兄ちゃんでいてほしい願い。気持ちと願いは両立できない。同じくらい強い二つの感情の間で揺れて、試合観戦のたびに胸がちょっぴり苦しくなるけれど。
和香は、きゅっ、と軽く拳を握る。
「お兄ちゃん、がんばれ」
和香が試合途中でお兄ちゃんの応援を放り出したことは一度もない。
人気になってから近付いて来るようなミーハーな女の子たちと私は違う。和香は心の中でそう繰り返す。
あの子たちは知らない。お兄ちゃんが野球だけじゃなくて料理も上手なこと。得意料理はゴーヤチャンプルなこと。洗濯物をシワなく干せること。動物にはよくなつかれるけど、本人は猫アレルギーなこと。
(お兄ちゃんのかっこいい姿を誰より知っているのは、他の誰でもない、私よ)
胸の中でそう唱えると、溜飲が下がった。
◇
大学で野球部に入っているお兄ちゃんは、帰りが遅くなることが多い。
だから和香は学校から帰宅する時、いつも祈りながら扉を開ける。今日はお兄ちゃんが早く帰ってきていますように。今日くらい部活がお休みになりますように。お兄ちゃんが休みの日に、勉強を見てもらうのが和香の大事な楽しみだった。
今日もまた、願掛けしながらドアノブを握る。
「ただいま」
ドアを開けたとたん、和香はその場に凍りついた。玄関に一足、可愛いミュールが置いてある。お兄ちゃんの靴の横に、寄り添うように並んでいる。これはお母さんの靴じゃない。もっと若い大人の女の人が履く靴だ。世界にはこんなに可愛い靴があって、それを履く人がいることにも驚いた。和香はヒールのある靴を履いたことがない。
(誰?)
和香は震える手で玄関にあるミュールをつかんだ。艶やかなエナメルの高そうな靴だった。細いヒールには傷一つついていない。
(……まさか。まさか。まさか。血の繋がっていない姉がいたの? 女友達? まさか、彼女、だなんてことは)
めまいに襲われて、玄関で両膝をつく。
(……今までこんなことなかったのに、どうしていきなり……? この人がお兄ちゃんに近づく理由は? ……ああ、わかった。プロ野球選手の妻になりたいのね。私のお兄ちゃんは試合で大活躍して、ドラフトから指名されるような素晴らしい選手になって、メジャーにも行く予定だから……手の届かない存在になる前に目をつけておこうって算段なんだわ)
和香はミュールを握り締めながら、決意した。
(……阻止しなきゃ。お兄ちゃんのためにも)
リビングに続くドアを開ける。
「和香、おかえり」
和香を出迎えてくれたお兄ちゃんの隣には、肌の白い女の人が座っていた。その女の人は、おじゃましています、と穏やかに微笑んだ。
目を合わせたくなかった。和香は彼女の足元を見つめる。その華奢な足の指には桜色のペディキュアが施されていた。視線のやり場に困って、今度はお兄ちゃんの黒い靴下に目を向けた。
「夏希といいます。妹さん、だよね」
「……お兄ちゃん。このひと、同じ学校の人?」
「ああ。俺の彼女だよ」
「おっ、おれのっ……かっっ」
自分の舌を思い切り噛んでしまった和香は口元を押さえた。両手で押さえていないと、唇の隙間から明日を生きる気力が抜け出てしまいそうだった。
「和香、唇から血がでてる」
「ちょっと噛んじゃっただけよ」
「そうか……。いや実は、大学からうちが近かったから、一緒にここで勉強することになったんだよ。今、テスト前だから図書館も喫茶店も混んでるからな」
「あまり長くお邪魔するのも申し訳ないし、あたしそろそろ帰った方がいい?」
「大丈夫だよ。母さんも夏希がうちにきてくれるの嬉しいみたいだし」
「よかった」
二人はほがらかに笑った。和香は蚊帳の外だ。夏希さんと目が合う。挨拶すらしていないことに気づいた和香は、
「……はじめまして」
と頭をさげてから、すばやく階段を駆け上がった。下のリビングから「ごめんな、うちの妹少し人見知りで」とお兄ちゃんが謝っているのが聞こえた。人見知りなんかじゃないわよ、と和香は奥歯を噛み締めて、自分の部屋に閉じこもった。床に寝転ぶと、下から夏希さんとお兄ちゃんの笑い声がする。
ついにこの日がきてしまった。
お兄ちゃんは年頃だし、かっこいい。彼女ができない方がおかしい。理屈ではわかる。けれど和香は床に倒れこんだまま動けなかった。いざ現実になると、とても受け止められそうになかった。
それなのに、夏希さんはあの日以来、よく家に遊びにやってくる。
「和香、今日も夏希、家にくるから」
「わかったわ」
がちゃ、と和香は玄関のチェーンロックをかけた。
「……和香、ロックははずすよ」
「ごめんなさい、つい。私がはずすわ」
「……どこか外に遊びに行ってきたらどうだ?」
「家にいるわ。今日はちゃんと夏希さんに挨拶したいの」
和香は無意識のうちにかけたチェーンロックをはずす。こないだは「はじめまして」の挨拶ができた。今日の目標は「こんにちは」を言うことだ。
お兄ちゃんが選んだ道なら応援するのが妹の務め、と言い聞かせ、夏希さんが来るのに備えた。
◇
玄関の呼び鈴が鳴った瞬間、背筋が伸びる。
「おじゃまします」
夏希さんは夏らしい黄色のワンピースをきて、麦わら帽子をかぶっていた。
「っこ……こん」
こんにちは、と挨拶しようとした和香は口を閉ざした。お兄ちゃんが、まるで王子様みたいに夏希さんの手を取ったからだ。舞踏会に参加する令嬢をエスコートするように、玄関からリビングへと夏希さんを導く。
廊下からリビングに続く敷居をまたぐ時には、
「少し段差あるから、気をつけて」
と囁く有り様だ。
「そこ、大した段差じゃないわよ……」
和香は小さく悪態をつく。お兄ちゃんは照れくさそうに微笑むばかりで、それが余計に癪に障った。
「和香ちゃん、ケーキ買ってきたから三人で食べよう。チーズケーキと、オペラ、ピスタチオのもあるけど、どれが好き?」
「それは……」
お兄ちゃんはチーズケーキが好きだった。三つあるケーキのうち一つだけは、確実にお兄ちゃんのために選ばれたものだ。
「……なんでもいいわ」
「和香の好きなチーズケーキがあるぞ」
和香がチーズケーキが好きなのは、それがお兄ちゃんの好物だからだ。同じものを食べて、おいしいね、と笑い合うのが好きだからだ。お兄ちゃんの鈍感さに苛立ちながら、和香は低い声で「じゃあ、チーズケーキを……」とつぶやいた。
「チーズケーキね、了解」
夏希さんは微笑んで、「食器借りてもいい?」とお兄ちゃんに尋ねた。お兄ちゃんと夏希さんが二人でキッチンに立ち、お茶の時間の準備をしている。並んでキッチンで作業している様子が、仲の良い父さんと母さんの姿に重なった。
「じゃあ、あとはあたしがやるから座ってて」
「夏希が客なんだから、ゆっくりしてていいんだぞ?」
「いいのいいの」
夏希さんに促されて、お兄ちゃんは席に着いた。和香はすかさず、その隣の席を確保する。
「和香ちゃんも座ってゆっくりしててね」
お茶を淹れ終えた夏希さんは、お兄ちゃんの向かいに座った。三人でダイニングテーブルを囲む。
夏希さんが買ってきてくれたチーズケーキには、艶やかなブルーベリーと小さなミントの葉がのっていた。チーズケーキを睨む。フォークを握る手が動かない。この黄金色の菓子が、賄賂に見えた。このチーズケーキを食べた瞬間、何もかも受け入れなければならないような気がした。おいしい、と褒めた瞬間に、二人の仲を認めたことにならないだろうか。
食べないの? と夏希さんに聞かれた和香は、
「……やっぱり、お腹いっぱいだわ」
と席を立つ。未練がましくチーズケーキを一瞥してから、階段を上がると、お兄ちゃんの部屋の前で足を止めた。扉がわずかに開いている。和香は部屋の中に体を滑り込ませた。
お兄ちゃんの部屋はお日様のにおいがする。壁に毎日の練習メニューと時間割が貼ってあるだけの質素な部屋なのに、暖かい。
お兄ちゃんのベッドに座る。布団が少し乱れていた。今朝までお兄ちゃんが寝ていた布団に目をやる。子供のようにもぐりこみたくなる気持ちを抑えながら、ベッドの上で膝を抱えた。ここは聖域だ。幼い頃から、和香が小さな恐れや不安を抱いた時に来ていた安らげる場所。無断でお兄ちゃんの部屋に入ったのは久しぶりだった。
いつからか、お兄ちゃんに素直にワガママを言えなくなった。
小さい頃はお兄ちゃんと同じ布団で眠っていた。お兄ちゃんは友達を作るのが苦手な和香の遊び相手になってくれたし、和香がいじめられている時には必ず助けてくれた。お兄ちゃんは妹の私を守り続けてくれるのだと、和香は思っていた。それがいつしか、お兄ちゃんは和香を守る騎士ではなく、自分のために戦う戦士になった。そして、頑張るお兄ちゃんを見守り応援するのが和香の心の支えになった。
けれど、いつまでお兄ちゃんを、そばで見守っていられるんだろう。
がんばれ、と叫ぶほどお兄ちゃんの後ろ姿は遠く小さくなっていって、いつか和香の声も届かない場所まで行ってしまうのではないかと思う。
和香は足の指を丸めた。どこかに力をいれていないと、弱音ばかりが溢れそうだった。
部屋の電気がついた。
「どうしたんだ。ここは俺の部屋だぞ?」
お兄ちゃんの声がして、膝を抱えていた和香は顔を上げた。
「お兄ちゃん。彼女なんてつくるべきじゃないわ」
「…和香は、夏希がきらいなのか?」
「きらいではないけど。恋人ができると練習に身が入らなくなったりするでしょう? お兄ちゃんはプロ野球目指してるんだから……」
「ははは。でも、応援してくれる人がいて頑張れることだってあるさ」
私の応援だけじゃ足りない? と言いたいのを堪える。
「今日、母さんは父さんとデートする日だから、夕飯は自分たちで食べて、だってさ。だから、夜になったら夏希と俺で何かおいしいものでも作るよ」
「夏希さん、料理もできるのね」
「ああ、面白くて優しいお姉さんだからな。気が向いたらいつでも来いよ」
「……気が向いたらね」
和香はお兄ちゃんに背を向けた。部屋の扉が閉まる。いつまでもこのままじゃだめ、と和香は自分の頬をつねった。
勢いよく立ち上がる。目の前がちかちかした。低血圧気味の体に活をいれ、ゆっくりと、つま先から階段を下りていく。壁にへばりつき、リビングにいる夏希さんを覗き見た。雑誌を読んでいるようだ。お兄ちゃんはキッチンで麦茶を淹れている。
和香は呼吸を整えると、また一歩足を進めた。少しずつでも、夏希さんに近づく作戦だ。「こんにちは」くらいはきちんと言いたかった。お兄ちゃんの妹としての礼儀は守ると心に決めて、また一歩近づく。
「和香ちゃん」
夏希さんは和香の姿を見て、嬉しそうに微笑む。忍び足で歩いていた和香は、体をこわばらせた。
「和香ちゃんは、海と山だったらどっちが好き?」
質問の意図がまるでわからなかった。
「えっ……どちらも別に好きではないわ」
「そっかー。和香ちゃんはあまりアウトドアはしないのかな」
「俺は山が好きだよ。体に良さそうじゃないか? 森林浴もできるしさ」
お兄ちゃんは山の方が好きなのね。和香はリビングで立ちすくむ。夏希さんが家に来るようになってから、お兄ちゃんの知らない顔が増えて行く。
「今度、夏希と一緒に出かけようと思ってるんだけど、よかったら和香も来ないか? 三人でどこかに行こう」
「さっ……三人で……?」
後ずさる和香に目もくれず、お兄ちゃんは夏希さんの隣に座った。昔から和香の特等席だった場所、そこは今、夏希さんのものだ。
「……出かけるなら、二人で行ってくればいいじゃない」
「せっかくだから和香も来た方がいいだろ。最近、家族旅行もしてないし。それに夏希、いい人だから和香とも仲良くなれるよ。なんでも相談できるお姉さんができたら和香も嬉しいんじゃないか?」
「私に気を遣わないで、二人で行けばいいじゃない」
和香は絞り出すように答えた。お兄ちゃんは眉をひそめる。
「……和香ちゃんごめんね、気を遣ってるわけじゃなくて。ええと…」
夏希さんは難しい顔をして、懸命に言葉を探している。私と仲良くなることに必死にならないでほしい。和香は拳を強く握る。
「……和香、どこ行くんだ?」
「お手洗いに行くだけよ」
和香はリビングをまっすぐつっきると、お手洗いの前を素通りして玄関の鍵を開けた。
「……和香ちゃん?」
夏希さんが心配そうにしているのが癪に障った。
(放っておいて欲しい、私にもお兄ちゃんにも関わらないでほしい、夏希さんのことなんか忘れたい)
和香は玄関の扉を開けて勢いよく家を飛び出す。
「和香ちゃん!」
夏希さんが和香を呼ぶたびに、逃げ足が速くなる。
◇
やみくもに走った。
走って走って、家から少しでも遠く離れれば何もかもリセットされればいいのにと思った。怒りも悲しみも収まり、彼女がいなくなり、お兄ちゃんはいつも通り。そうなればいい、とありえない現実を願いながら走った。すぐに息は苦しくなり、足はだるくなったけれど、体が辛くなればなるほどもっと遠くまで走りたくなった。足を止めて体の痛みが消えたら、心の痛みに捕まってしまいそうだった。
「あっ……」
足がもつれた。とっさに地面についた手のひらには擦り傷ができ、履いていたタイツのひざが破れた。
時間をかけながら体を起こすと、和香はとぼとぼ歩き始める。何もない住宅街を歩き、公園を通り抜け、寂れた商店街をさまよう。どことなく見たことのある景色が続くけれど、ここが家からどのくらい離れているのかわからなかった。
お腹も減ったし、喉も渇いたし、できればどこかに座りたかった。力なく商店街を歩いていると、ふわふわしたものが視界に飛び込んできた。
「?」
和香はおもちゃ屋の前で足を止める。
昔に放送されていたアニメ、ベアマックスの着ぐるみがおもちゃ屋の前でしきりに手を振っていた。
(……ベアマックスだ……)
ベアマックスのアニメは、和香が生まれる前の作品だ。けれど和香は、小さい頃に縁日でお兄ちゃんからもらったベアマックスの人形を今でも大切にしている。だからこそ、ベアマックスは和香を助けに来てくれたんだ。今でもお兄ちゃんとの思い出の人形を大事にしてくれている和香に恩返しに来てくれたんだ。何かしらの形で、想いは報われるらしい。和香はベアマックスに向かってぎこちなく手を振り返す。
すると、ベアマックスは両手で手招きをした。
「……」
和香はベアマックスに近づくと、そのふわふわした体を軽くハグした。温かくて優しい誰かに抱きしめられたかった。誰か、といいつつ抱きしめられたい相手はお兄ちゃんただ一人だ、けれどそんなワガママはとても言えない。ベアマックスは和香を抱き返してはくれなかった。和香は、ぎゅう、と腕に力を込める。ベアマックスは困惑したように体を斜めに揺らす。
「うわー、でかいクマだ!」
「スーパーキックしてやる!」
かけてきた二人の幼児に押されて、和香は着ぐるみから離れる。振り返ると、そこにいるのはベアマックスではなくて、ただの白いクマの着ぐるみだった。幼児に蹴られて、痛そうに腰を丸めている。
(……ベアマックスが、来てくるわけないじゃない……)
和香はただの着ぐるみと子どもたちに背を向けて、またよろよろと歩き始める。この世には、自分のものなんて一つもないんだと思った。
◇
すっかり日が暮れて、街頭の灯りが一つ二つと灯されていく。飛び出してきた手前、いそいそと帰るに帰れなかった。夏とはいえ、夜になると肌寒い。和香が公園のブランコに腰掛けて、お茶を買う小銭くらい持ってくればよかったと後悔している時だった。
「見つけた」
背中が温かい。お兄ちゃん? と期待した心がしぼんでいく。鼻先をかすめたのは、ジャスミンのように華やかな、女の人の香りだった。
「夏希さん……?」
「すごく心配したよ。どうしたの?」
後ろから和香を強く抱きしめた後、夏希さんは和香の正面に回った。背中に残るぬくもりが何故か名残惜しかった。
「どこに行ったのかと思ったよ。お兄ちゃんも心配してるから、お家戻ろう」
「……なんで、探しに来てくれたんですか」
「うーん、なんでだろうね。わからない。けど、和香ちゃんのことがちょっと気になるからかな」
「どうして気になるんですか」
「えー、うーん。あたしは一人っ子だったから。兄妹の絆みたいなものにちょっと憧れるんだよね。それに……」
その憧れは、妹への嫉妬ですか。和香は夏希さんと目を合わせた。正面からまっすぐに夏希さんと対峙するのはこれが初めてだ。
「それに?」
夏希さんの答えを急かす。夏希さんは照れ臭そうに苦笑した。
「好きな人が大事にしてる人は、あたしも大事にしたいって思うからかな」
和香は力なく唇を開くと、ゆっくり息を吸い込んだ。ああ、と心の中で大きなため息をつく。
夏希さんがもっと、嫌な女だったらよかった。
そうじゃないから、これ以上夏希さんを拒めない。お兄ちゃんは素敵な人と付き合っている。それはお兄ちゃんにとって幸福なことだ。素直に喜べない自分が惨めだった。
「あれ、和香ちゃんひざ怪我してるよ? 消毒液買ってこないと……」
「お兄ちゃんは……」
「家で夕飯つくって和香ちゃんのこと待っててくれてるよ」
「……帰ります」
夏希さんが手を差し出す。和香はおそるおそるその手を握った。擦り傷が少ししみたけれど、夏希さんの手は柔らかくて、気持ちよかった。
◇
家に帰ると、食卓にはゴーヤチャンプルとモヤシのお浸し、具沢山の味噌汁が並んでいた。青いエプロンをしたお兄ちゃんが振り返る。
「おかえり。ゴーヤチャンプル温めようか」
どうして、お兄ちゃんは追いかけてきてくれなかったの、と和香はお兄ちゃんの顔を見た途端、涙が溢れそうになった。
「いただきます」
三人で手を合わせて、お兄ちゃんの作ってくれたご飯を食べた。いつもよりゴーヤが苦く感じた。和香が家を飛び出したことには誰も触れず、野球の試合の話や、夏希さんの高校の思い出話なんかで沈黙が埋まっていく。
食事を終えると、夏希さんは帰り支度を整えた。後片付けできなくてごめんなさい、と申し訳なさそうにしてる夏希さんをお兄ちゃんは強引に玄関までせき立てた。おじゃましました、という夏希さんの声を聞き、和香は玄関に走る。
「夏希さん」
「和香ちゃん?」
驚いた顔で振り返る夏希さんに向かって、和香はそっと手を振った。
「また今度」
「またね」
夏希さんは嬉しそうに顔をほころばせる。お兄ちゃんは夏希さんを近くの駅まで送るといって出て行った。
作りすぎたモヤシのお浸しとゴーヤチャンプルが、タッパーに詰められてキッチンの脇に並んでいる。
夜更けのキッチンで、お兄ちゃんが洗い物をしていた。階段の陰からそれを見ていた和香は、お兄ちゃんに近づいた。
「お兄ちゃん」
油汚れを流す水の音がうるさい。お兄ちゃんは振り返らない。和香はお兄ちゃんの青いエプロンの紐に指をかける。ゆっくり紐をひっぱると、結び目がほどけていく。
「わっ、邪魔するなよー」
お兄ちゃんが水道を止めた。タオルで手を拭うと、少し面倒くさそうにエプロンを結び直す。蝶々結びを作る指先が、ごつごつしてて固そうだと思った。
お兄ちゃんは洗い物を続けながら、
「宿題は終わったのか?」
と和香に尋ねた。
「まだ、少し残ってるわ」
「じゃ、あとで見てやろうか」
「嬉しい」
これからも私だけのお兄ちゃんでいて、とは、言えなかった。和香は唇の端をきゅっと結ぶ。タイムカプセルを埋めた日の思い出を奥歯で噛みしめる。もう小さい頃のような、お兄ちゃんの大事な野球ボールを隠す妹には戻りたくはなかった。
和香はエプロンからはみ出しているTシャツの裾を握る。お兄ちゃんからは、暖かくて強いお日様のにおいがした。
わがままは言わない、だからもう少し、今はまだ、お兄ちゃんを支えに生きたい。
「お兄ちゃんのこと、応援してるから」
水音が止まる。汚れ物がなくなったシンクの上に、蛇口から雫がひとつ滴る。
お兄ちゃんはいつものように、ありがとう、と微笑んだ。