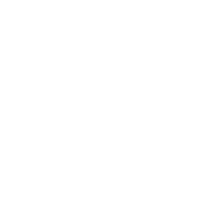第5話 宇喜多 茜「たずねびと」
小学生の頃、鬼ごっこが苦手だった。追いかけられるのは怖いし、友達に逃げられるのは悲しい。茜は、鬼から逃げるのも、自分が鬼になるのも少し嫌だと思った。
水飲み場の陰に隠れながら、グラウンドで走るクラスメイトを見つめる。鬼役の男の子二人は足が速いだけでなく、ターゲットを挟み撃ちにするのが上手だった。鬼に捕まったクラスメイトたちは、次々とその場で彫像のように動きを止める。氷鬼だ。誰か一人が氷にされる度に、きゃー、と明るい悲鳴があがる。追いかける方も逃げる方も、なぜかとても楽しそうだ。
「……茜も、みんなと遊んでみたいけど……うぅ〜……」
茜は胸の前で両手をぎゅっと握りしめながら、鬼から逃げるクラスメイトを見守る。
水飲み場のそばで氷鬼を観戦していると、鬼役の男の子が休憩しにやってきた。茜は慌てて背を向ける。
「あれ、君って……」
「なっ……」
後ろから声をかけられた茜は、猫耳パーカーのフードを強く掴み、顔を隠す。鬼役の男の子は水で濡れた口を拳で拭いながら、茜に話しかけた。
「……君って、同じクラスだよね? 確か……宇喜多さんだっけ? ここで何してるの?」
「えっ、ええっと……」
「よかったら一緒にやる? 氷鬼」
茜は顔を上げる。強気に笑う男の子と目があった。途端に言葉を失って、一歩後ずさる。
「あっ……」
茜もやる。たった一言、そう言うだけでいい。茜は静かに息を吸いながら、唇を小さく開く。
「あっ……あか……」
「おーい、鬼がいつまでも休憩してたら、始まらないだろー」
グラウンドで鬼役の帰りを待っていたクラスメイトたちが叫んだ。その声が、茜の耳にはなんだか怒っているように聞こえた。
「ごっ、ごめんなさい〜」
「え?」
「ばっ……ばいばい〜!」
茜は鬼役の彼に背を向けて、逃げるように走り去った。
◇
何かあるとすぐ逃げ出してしまうあの頃と比べて、少しは大人になっているんだろうか、と時々思う。
バケツを持った幼稚園児が、道を遮るようにしてよたよたと歩いている。
「わっ! わぁぁっ」
茜は慌てて立ち止まった。幼稚園児は茜を無視して、バケツを大事そうに抱えながら近くの公園へ入っていく。公園の砂場では五人の幼稚園児が仲良く砂の城を作って遊んでいた。
「はっぱと小石、たくさんひろってきたよー。だからぼくも、仲間にいれて? いっしょにあそぼー」
「いーよー」
砂場にいる友達の答えを聞いて、バケツを持った少年は砂場に飛び込んだ。
幼稚園児ですら「あそぼう」と言えるのに、茜にはどうしてもそれができなかった。
砂場で遊ぶ彼らを見ながら、茜は目を細める。茜も幼稚園の頃には、この公園の砂場でよく遊んでいた。けれど中学生になった今、あの砂場はもう茜の居場所ではなくなってしまった。
なつかしいなぁ〜、とため息を吐くと、肋骨のあたりが少し痛んだ。急に走り過ぎたせいだろう。
休憩がてら、茜は公園の端にある滑り台に登った。サビだらけの滑り台は人気がなく、蜘蛛の巣と砂で汚れている。滑り台の上から公園を見渡した。小さな砂場と、ブランコ、それに動物のオブジェがあるだけの簡素な公園だ。ここって、こんなに退屈な場所だったっけ、と茜は訝りながら、唇に指を当てた。
体育すわりをして、くすんだ銀色の傾斜を一人で滑り降りる。一人で滑る滑り台は、あまりスピードがでなかった。何か物足りなくて、両膝をぎゅっと抱える。
公園が楽しくないのは、お兄ちゃんがいないせいだ。
まだ茜が幼稚園に入ったばかりで、周りの空気に全く馴染めずにいた頃。この公園で、茜の面倒を見てくれる男の子がいた。
彼と出会ったのは、砂場でイチゴのショートケーキを作っている時だった。爪の隙間まで砂まみれにしながら、上手な円筒を作るのに苦労していると、後ろから声をかけられた。
「このバケツ、貸すよ」
「ええっ…!?」
「これを使うと……ほら、できた」
彼は小さなバケツの中に砂を詰めると、ひっくりかえして美しい円筒を作った。そこに、生クリームのかわりに乾燥した白い砂を振り掛けて、イチゴに見立てた小石や、はっぱを飾り付けていく。
「わぁ……上手だねぇ〜」
茜が感動していると、彼は茜にバケツや、スコップを貸してくれた。その親切にどうお返ししたら良いのかと、茜がしどろもどろになっていると、彼は明るい笑みを浮かべる。
「一緒に作ろう」
その笑顔につられて、茜は自然と頷いた。人見知りの茜がはじめて仲良くなれたのが、その男の子だった。出会って以来、公園で一人ぼっちでいる茜にいつも優しくしてくれるから、茜は自然と彼を「お兄ちゃん」と呼ぶようになった。
お兄ちゃんとは毎日のように一緒に遊んだ。ブランコの二人乗りもしたし、二人で滑り台を一緒に滑った。一人で滑る時よりずっとスピードがでるから、目を回してしまいそうになった。何をしても楽しかったけれど、茜とお兄ちゃんは特に砂場がお気に入りだった。
「あっ、あのね……茜、泥だんご作るの、得意なんだよぉ〜」
仲良くなった証に、茜はお兄ちゃんに泥だんごを作ってあげた。
「ほんとだ。きれいなおだんごだなー。ここに飾っておこう」
お兄ちゃんは、砂場の縁に茜が作った泥だんごを置く。
「いつか、本物のおだんご作って、お兄ちゃんに食べさせてあげるね。お兄ちゃんは……茜の、たった一人の友だちだもん」
「茜はいい子だから、すぐにたくさん友だちできると思うよ」
「そっ、そんなことないよ……それに、茜は……お兄ちゃんがいればそれでいいよ」
「そういってもらえるのは嬉しいけど、なんかもったいないな。茜のいいところを僕がひとりじめしてるみたいで」
「そっ、それでいいよ……!」
茜がそういった時、お兄ちゃんが困ったように笑ったのを今でもよく覚えている。
あの頃は、お兄ちゃんさえいれば生きていける、と本気で思っていた。
なつかしくて甘い思い出に浸っていると、唇が半開きになっていた。茜は自分の両頬を軽く叩く。優しくしてもらった記憶を掘り返してばかりじゃ、大人になれそうにない。
茜色に焼けた空に、夕焼け小焼けのメロディが響く。もう五時だ。滑り台の下でうずくまっていた茜は立ち上がった。
公園で遊んでいた子どもたちも、親に手を引かれて去っていく。いなくなる子どもたちの姿を見つめながら、あのお兄ちゃんは今どうしているんだろうと思った。今日みたいに遊びの輪に入れなかった日には、お兄ちゃんと遊んだ日のことが恋しくて胸が痛む。
お母さんがいうには、大人になるにつれてたくさんのものが消えていくらしい。サンタクロースもいなくなったし、葉っぱの裏にいるカタツムリもだんだん見つけられなくなっていくし、夏が待ち遠しい気持ちも薄れていくようだ。
お兄ちゃんが茜の前からいなくなったのも、きっと大人に近づいたせいだろう。歳を重ねるにつれて、お兄ちゃんと公園で会う機会も自然と少なくなり、やがて茜自身も砂場やブランコで遊ばなくなっていった。
◇
「ただいまぁ〜」
帰宅した茜は部屋の電気をつける。リビングで丸くなっていた亀の弥太郎の甲羅を撫でた。日向ぼっこしていた弥太郎は、茜の帰宅に気づくと、のっそりと首を伸ばす。
お母さんはまだ仕事から帰ってきていないようで、テーブルの上にはラップのかかった野菜炒めと卵焼きが置いてある。
『五〇秒チンして食べてね。ピーマンも残さず食べること!』
母のメモ書きを読むと、弥太郎に語りかけた。
「うぅ〜。なんでわざわざ、茜の嫌いなものつくるのかなぁ? もう……! 弥太郎、食べる?」
「……」
弥太郎は大きなあくびをした。茜はすかさず、その口にピーマンを突っ込んだ。
「……!」
弥太郎は目を見開いた後、ゆっくり咀嚼して飲み込んだ。
「うんうん、ゆっくり噛んで食べるんだよぉ〜」
茜はにこにこ笑いながら、自分の苦手な野菜を弥太郎に与えた。母子家庭の茜にとって、亀の弥太郎は大切な話し相手だ。
お母さんが帰ってくるのは、どんなに早くても夜の八時すぎだった。玄関で物音がして、弥太郎が首をもたげる。
「ただいま〜! 茜、ちゃんとご飯食べた? あら、ピーマンもちゃんと食べたの。えらいえらい」
帰宅したお母さんは、スーツを脱ぐより先に野菜炒めの皿を確認した。
「う……うん……」
「……本当に茜が食べたの? 嘘ついてない?」
「つ、つ、ついてないよ。茜を信じてよぉ〜」
「……また、弥太郎に食べさせたでしょ」
「う、うう〜! だって……嫌いなんだもん!」
「嫌いでも食べないと! お菓子ばっかり食べてたら体壊すわよ」
「嫌いなもの食べるより……ずっといいよぉ〜」
「わがままいわないの。食べたものは茜の体になっていくんだから」
「お母さん忙しいんだし……茜のためにご飯つくらなくっても、平気だよ?」
「え……?」
「茜も、わざわざ嫌いなもの……食べたくないし……」
「……そう」
お母さんは、一つに結い上げていた髪を解いた。お母さんの冷めた横顔を見て、茜は生唾を飲み込む。ひどいことを言ってしまった。
「あのっ、お母さん……」
「茜の言いたいことは、よーくわかったわ」
「おっ、お茶いれてあげるよ〜、あたたかいお茶飲むと、気分も落ち着くよ……」
「いらない。お母さんはもう寝るから」
「えぇ〜っ、お母さん……あのね……」
お母さんは茜に背を向けると、寝室の扉をぴしゃりと閉めた。リビングに取り残された茜は部屋の中を右往左往して、弥太郎に助けを求めた。
「お母さんに……なんて謝ったら、許してもらえると思う……?」
けれど弥太郎は、我関せずといった様子で、すました顔をしている。
「……せめて、お皿くらい洗っておこうかなぁ〜。そしたら、少しはお母さん喜んでくれるかも。ね、弥太郎……」
茜は、ほとんどお母さんの私有地になっているキッチンを見渡す。
シンクのそばに、無臭のハンドクリームがおかれていた。もちろんお母さんのものだ。家でも外でも働きづめのお母さんの指先はいつもささくれている。
三角コーナーには、出汁をとる時に使った煮干しと昆布が捨てられていた。コンロに置かれた片手鍋のふたを開けると、お母さんが作り置きしてくれたお味噌汁が残っている。シジミがたくさん入った、具沢山で汁が少ない味噌汁だ。茜が一人でお腹を空かせてしまった時のために、冷凍庫にはおにぎりとホットケーキが何個か冷凍保存されている。お母さんは、決して手抜きの家事をしない。
もっと、楽をしていいよ。と、お母さんに伝えたかった。けれどそれは、最悪の形で空回りしてしまった。茜は冷蔵庫の扉に寄りかかる。
自分の気持ちを上手に言うことができない。友だちもうまく作れない。できないことばかりだけど、人に優しくされてばっかりで、優しくできない大人にはなりたくなかった。
お兄ちゃんにはたくさんよくしてもらったのに、何もお返しができずにお別れしてしまった。せめてお母さんには、何かお返しがしたい。
「……茜が晩ご飯作ったら、お母さん喜んでくれるかな……」
弥太郎は、首をゆっくり縦に振った。
「どんなのだったら……茜にも作れるかなぁ〜……包丁を……使わない料理がいいな……」
弥太郎のそばで、お母さんがよく読む料理雑誌を引っ張り出しながらメニューを吟味する。雑誌に載っているのはどれも、切ったり焼いたり下ごしらえが必要なものばかりだ。茜は雑誌とにらめっこしながら、どうしよぉ〜、と唇を噛んだ。
「弥太郎は……なにが食べたい?」
「……」
弥太郎は料理雑誌にお尻を向けて、首をふる。
「弥太郎は……おなかいっぱいなんだね。さっき、ごはん食べたもんねぇ……」
茜は料理雑誌をめくりながら、弥太郎の背中を撫でた。
「茜でも……簡単に作れそうなもの……ないかなぁ。……おままごとみたいには、作れないよねぇ〜」
本当の料理は難しい。おままごとの中でなら、どんなものでも作ったことにできた。ちぎった葉っぱを器にいれてお味噌汁だよ〜と差し出したり、砂場で作った泥だんごをご飯にしたり。おままごとの最中は、水や草やお花、泥なんかの公園にあるものを使って、いろんな料理を作った気になれた。現実では、そうはいかない。
「手作りお月見団子」のレシピを見ながら、泥だんごを作るのは昔から得意なんだけどなぁ〜、と茜は料理雑誌を枕にして、ため息をついた。
「……おだんご?」
茜は顔をあげた。砂場が茜の遊び場だった頃、大きくなったらいつか本物のおだんごを作ってお月見したいな、と夢見ていたことを思い出した。
「そうだっ、おだんごにしよ〜! ほんもののおだんごを作ってみよ〜。茜ももう……昔より大人になったから……」
茜はぴょん、と飛び跳ねて、お母さんが驚く顔を想像しながら眠りについた。
◇
茜の料理作戦は、土曜日の朝から実行された。やり残した仕事があるからと会社に向かうお母さんを送り出し、茜は弥太郎と目配せをする。
弥太郎と二人きりになると、茜は一人で拳を天井へと突き上げ、気合を入れた。
「よーし、がんばるぞぉ!」
弥太郎は、大きなあくびをした。
「まずは……材料を買ってこないと〜。ねえ、弥太郎……一緒にくる?」
弥太郎は、のそのそと窓辺へ歩き、日向で丸くなる。
「……弥太郎? お散歩いかない……?」
弥太郎は太陽の光を浴びて、気持ちよさそうに目を閉じた。
「じゃあ……弥太郎はお留守番、がんばってね」
茜はアヒルの貯金箱に入れていたお年玉を握ると、お団子の材料を買いに家を出た。
白玉粉、お水、お塩……おだんごの材料はとてもシンプルだ。砂糖と醤油とみりん、片栗粉を混ぜれば、みたらしだんごのタレも作れる。
調味料はキッチンに常備されていたから、茜はスーパーで白玉粉だけを買い足した。スーパーの袋を大きく振り回して、鼻歌交じりに家に向かう。
なつかしい公園の前を通りすぎる時、少しだけ歩調が緩やかになる。何の素性もわからないお兄ちゃんとの茜をつないでいるのは、この場所で作った思い出だけだ。
「いつか……また会えたらいいなぁ……」
同じ場所で会えるとは限らないのに、つい夢を見てしまう。
鼻歌の続きを歌いながら、再び歩き出した時だった。公園から、男の子の声がした。
「昔っから、この砂場は大人気だなぁ」
どこかで、聞いたことがあるような声だった。少し声変わりしていても、言葉に温かみと優しさがにじみ出ている。もしかして、と茜は辺りを見回した。家族連れや、幼稚園児たちに混じって、細長いベンチの両端に、男の子と女の子が座っていた。茜の位置からでは、二人の背中しか見えない。一人分離れた隣に座る女の子は、彼女だろうか。恋人ならもっと近くに座るだろうから、そこまで親しい関係ではないのかもしれない。
「僕、ここの砂場が好きで。よく遊んだんだよ。その時、仲よかった女の子がいてね。砂のお城とか泥だんごとか、よく作ったなぁ」
聞き耳を立てながら、スーパーの袋を握りしめる。その、『仲よかった女の子』は、もしかして自分のことだろうか。
人違いである可能性の方が高いのに、どこかで期待してしまう。
もしお兄ちゃんが今もこの街に住んでいるのなら、この公園でお兄ちゃんを見かけることがあっても、おかしくはない。
あれから何年も経った。お兄ちゃんが茜のことを覚えているのかもわからない。けれど、「もしかしたら」の可能性に賭けないと、茜の望みは絶対に叶わない。
茜は、男の子が座るベンチに近づいた。手を伸ばせば届きそうな距離まで近づく。心臓が高鳴る。息を吐いた拍子に心臓が口から飛び出しそうだ。胸を押さえて、少しずつ唇を開く。声をかけたいのに、言葉がでない。喉が干からびて、ひりひりした。
「あっ……あのぅ……」
ようやく絞り出した声で話しかけると、目の前の男の子はゆっくり顔を上げる。目が合う前に逃げ出したいと思った。怯える足に力を入れる。
「……ん?」
男の子は、静かに目を瞬かせた。優しそうな人だった。弓形の眉が、その男の人の顔をより親切そうに見せている。茶色い瞳が茜を捉えた。
この人は、あのお兄ちゃんだろうか。身長もぐんと伸びたし、喉仏もある。柔らかかったはずのほっぺたには頬骨がでているし、華奢だった手足には筋肉がついていた。
男の子は、中学校の三年間でぐんと様変わりするらしい。声をかけたのはいいものの、目の前の男の子が、昔よく遊んでくれたお兄ちゃんだと確かめる方法が思いつかなかった。
「えっ、えーっと……あの……あ、茜……」
茜は猫耳パーカーの紐を強く握りながら、次の言葉を探す。心臓の音はますます大きくなって、耳の裏まで熱かった。
「貴女、兄に何か用かしら」
茜がしどろもどろになっていると、長い髪を一本にまとめた、スポーツジャージ姿の女の子が茜に話しかけた。彼女と男の子の間には大きな野球バッグが二つ置いてある。二人の距離が妙に開いているのはこのバッグが原因だった。
「あっ……」
茜はフードを深くかぶりなおし、一歩後ずさった。
「う〜ん……もしかしたら、球場で会ったのかも」
「知り合いじゃないのね」
「う、うーん。人の顔を覚えるのが苦手で」
「自分を応援してくれる女の子の顔くらい、少しは覚えてあげたらどう?」
「龍は覚えてるの? 応援してくれる人の顔」
「試合中、スタンド席のことは目に入らないの。貴女は、野球が好きなの?」
「やっ……野球……?」
突然話を振られた茜は、困惑して視線を泳がせた。
「野球場で兄を見かけたわけじゃないの?」
「ええと……あ、茜……お、お兄ちゃんを、探してて……っ」
「ごめんなさい。早とちりしちゃって。兄は甲子園に出て以来、道で声をかけられたりするものだから。貴女のお兄さん、見つかりそう? 探すの手伝いましょうか」
「だっ……大丈夫だよぉ〜。きっと、そのうち見つかる……と、思う……」
「そう。会えるといいわね。きっと、お兄さんも貴女のこと探してるだろうから」
そう言うと、女の子は涼やかに微笑んだ。茜の頬が真っ赤に染まる。
「……あっ、ありがとうございましたぁ〜」
茜は軽く頭を下げると、その場を立ち去った。いきなり声をかけたりして、なんてことしちゃったんだろう、と恥ずかしさで体が熱くなるけれど、不思議と帰る足取りは軽かった。
◇
家では、弥太郎が料理本の上で寝ていた。
「弥太郎、レシピ見ててくれたの?」
弥太郎は首をもたげると、口で買い物袋を引っ張った。
「あわ〜、早く作らないと、お母さんが帰ってくる時間に間に合わないね……!」
茜は両手を綺麗に洗うと、塩に砂糖、片栗粉と醤油を並べた。
弥太郎が短い足で料理本を蹴飛ばす。
「わっ、わかってるよ〜」
弥太郎に急かされるようにして、茜は料理本を開く。
さっき道端で出会った男の子のことを思い返すと、レシピが頭に入ってこなかった。お兄ちゃんは一人っ子だったはずだから、さっきの男の子は茜が探すお兄ちゃんではないだろう。人違いだったけれど、知らない人に自分から声をかけられたことは、大きな前進だ。
みんなとの鬼ごっこに参加できない、クラスメイトと楽しく会話することもできない。けれど、お兄ちゃんに会えるかもしれないと思えば、茜はどんなことでも挑戦できそうだった。
(大切なひとのためなら……茜、なんでもがんばれる……かも……)
茜は腕まくりして、おだんご作りにとりかかることにした。
「今は……お母さんを喜ばせることが一番大切だからね!」
弥太郎は首を重たそうに動かして、頷いた。
銀色のボウルの中で白玉粉と水を混ぜる。耳たぶくらいの固さになるまでこねた。粘土遊びをしているようで楽しい。上機嫌になった茜は、弥太郎に話しかける。
「……なんだか、おいしく作れそうな気がするよぉ〜」
「っくしゅ……」
床にこぼれた白玉粉を浴びた弥太郎は、くしゃみをした。真っ白になった顔を揺らしながら、体にかかった粉を振り落としている。
キッチンや弥太郎を粉まみれにしながら、なんとかおだんごの生地を作り終えると、茜はタレ作りに取りかかった。
「あちっ……」
みたらしのタレを真っ黒に焦がしてしまい、なんども作り直すうちにキッチンのシンクまで黒く染まっていく。タレ作りは、おだんごの生地をこねるよりずっと難しかった。
「これで、どうかなぁ……」
三回目につくったみたらしのタレを弥太郎に毒味させると、弥太郎は苦々しそうに首を振った。
「うぅ〜……どうして苦くなっちゃうんだろ……」
茜はキッチンにしゃがみこんで、弥太郎のごつごつした甲羅に触れる。弥太郎はつぶらな瞳で茜を見上げた。どんな時でも、弥太郎がそばにいてくれるのが心強い。
「よぉ〜し! もう一回がんばろぉ〜!」
茜は再びキッチンに立った。四苦八苦して、ようやく苦くないタレが出来た時、玄関の扉が開いた。
「ただいまー。……茜? なんだか部屋が焦げ臭いんだけど……?」
「お母さん、おかえり〜! あのね、今日の晩ご飯は……茜が作ったよ!」
「晩ご飯って……?」
「じゃじゃ〜ん! みたらしだんごです」
「これ、自分で作ったの?」
「そうだよぉ〜! いつも、お母さんがご飯作ってくれるから……たまには茜が作ろうと思って……」
「……あのね、おだんごはご飯じゃなくて、お菓子です。茜はまたお菓子ばっかり……」
お母さんは飽きれたように自分の額に手を当てる。それから、お皿の上にある不格好なみたらしだんごを見て微笑んだ。
「でも、ありがたくいただくわね」
「食べて食べて〜。お茶もいれてあげるね!」
茜は急須に入れた緑茶をテーブルに運ぶ。お母さんは、みたらしだんごを一つ頬張った。弥太郎と茜は、お母さんが咀嚼するのをじっと見守る。
「……うん。おいしい」
「よかったぁ!」
「そのうち、もっといろんな料理作れるようになるといいね。お母さんが教えてあげるわ」
「うん! 茜、がんばって覚えるよぉ〜」
「それから茜。キッチンはちゃんと自分で片付けてね」
「わっ、わかってるよ……」
茜は、焦げたフライパンや鍋、粉まみれのまな板が散乱するキッチンを横目に、苦笑いした。
お母さんとの夕飯を食べ終えて、片付けを終える頃には夜の九時を回っていた。
茜は余ったおだんごをお皿に乗せて、窓を開ける。ベランダに出ると、弥太郎も茜の後に続いた。昼間はうるさかったセミも夜には寝静まる。夜風で揺れる葉の音だけが、夏の夜に染み渡った。
「今日が、満月だったらよかったのにねぇ〜」
弥太郎に話しかけながら、茜は星空を見上げる。下弦の月が、暗い雲の上にぼんやりと浮かんでいる。茜は、おだんごを乗せたお皿をベランダに置いた。これはお兄ちゃんの分だ。直接渡すことはできないから、代わりにお月さまの下にそなえた。
「この街って、広いのかなぁ〜……」
ベランダの手すりを掴んだ。公園で出会った女の子の言葉を思い出す。
『きっと、お兄さんも貴女を探してるだろうから』
眼下には、車のヘッドライトや、カーテンからこぼれる灯が何百と広がっていた。その何百もの光に向かって、「茜なら、ここだよ」と囁いてみたくなる。
黙って景色を眺めていると、後ろから弥太郎が首を伸ばし、とがった唇でおだんごをつつく。
「あーっ!」
茜が気づいた時には、時すでに遅し。弥太郎はおだんごを強靭な顎で噛み砕いている最中だった。
「……これは、弥太郎のじゃないのにー!」
語気を荒らげながらも、不思議と怒る気にはならなかった。お兄ちゃんと会えなくなってから、弥太郎はずっと茜の遊び相手でいてくれる。
茜は弥太郎の甲羅に頬を寄せた。弥太郎は少し迷惑そうに瞬きをした後、心地よさそうに手足を引っ込めて、体を丸めた。