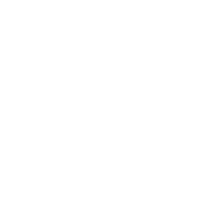第4話 河北 智恵「夏の青写真」
「女の子でも甲子園を目指せる世界にするんだ!」
翼がそう言いだしたのは、夏の甲子園が終わった頃のことだった。厳しい残暑の中で、蝉が懸命に鳴いている。
中学最後の公式戦を終えて以来、ずっと元気をなくしていた翼が久しぶりに饒舌になるのをみて、智恵も頬が上気した。
「いいね、それってすごく素敵だよ!」
「ソフトボールに転向することとか、選手を諦めてマネージャーになることも考えたけど……私はやっぱり、今までみたいに野球がしたいし、大舞台を目指して勝負したいから。そのために、できることはなんでもやってみようと思って」
翼の澄んだ瞳がきらりと輝く。智恵はトートバッグから取り出した小さなメガホンを振り上げた。
「私も手伝うよ。翼が活躍するところ、もっと見ていたいから。いつか晴れ舞台に立てるといいね」
「ありがとう! 何から始めようかな。いろいろ考えたんだけどね……」
翼は智恵の耳元に唇を寄せた。大きな野望が隠された、二人の秘密計画。智恵は穏やかに微笑みながら、翼が語る未来の話に頷いた。
それから署名を集めたり、甲子園に出たいという思いを綴った長い長い手紙を書いては、学校の先生をふくめ、考えつく限りの方々へ送ったりした。けれどいくら訴えかけたところで思いは実らず、現時点ではどうあがいたところで、女子が高校野球の大舞台・甲子園を目指すことは不可能だった。
それから数ヶ月後に翼の元には何通もの返事が返ってきたけれど、どの手紙の書き出しもすべて『誠に残念ではありますが』ではじまっていた。
最後に届いた一通の手紙を翼は何度も何度も読み返す。何度読み返したところで内容は変わらない。それでもまだどこかに希望があってほしいと信じているみたいに繰り返し文章に目を走らせる。
「……仕方ないよね。これだけやっても無理だったんだもん。もう、あきらめるよ。ともっち、たくさん手伝ってくれてありがとう」
翼は無理矢理微笑んで見せた。
「力になれなくてごめんね」
「私ががんばれるのはともっちのおかげだよ! 気持ち切り替えてこう! そろそろ進路のこと考えないとね。陸上の推薦は蹴っちゃったし、どうしようかな……」
届いた手紙をたたみ直すと、学校の机の奥に突っ込んだ。その翌日、翼は38度の熱を出して学校を休んでしまった。
「有原が休みなんて珍しいな」
クラスの男子が、帰宅際に翼の机を一瞥した。
「そうだね。ちょっと風邪引いたみたい」
「へー、うつされないように気をつけねーと。それじゃ!」
「じゃあね」
ぽつりぽつりと同級生が帰宅していく。放課後のチャイムが鳴る。智恵は、翼の机を指先で撫でた。
(あの手紙が、ショックだったのかな……)
翼のいない教室は、いつもより少しだけ寒々しく感じる。灰色の秋風が智恵の頬をかすめた。教室のカーテンが音もなく揺れる。智恵は翼の机の中に手を入れた。そこには今日配布された学級通信や進路面談日程表、保健だよりに混じって、「甲子園に出られない」という事実をつきつける手紙が入ったままになっていた。すでに開封されたその手紙には何度も折り返した跡が残っている。翼は一体、何回この手紙を見返したんだろう。
『誠に残念ではありますが、現在の規則では女子生徒の出場は認められません』
明朝体で書かれたその一文はなんだかとても素っ気なかった。智恵は、翼がいつまでも捨てられずにいるその手紙を、カバンのなかへしまった。
「河北、待たせて悪かったな。進路面談始めるか」
会議を終えた先生が教室の扉を閉めた。掃除を終え、空気を入れ替えたばかりの教室で机を向かい合わせる。
「河北の成績だったら、もっと偏差値の高いところ行けるぞ」
「今回のテストは、がんばりました」
「いい調子だ。せっかくだから、ここチャレンジしてみたらどうだ」
悩んでいる智恵を見て、先生は高校のパンフレットを机に置いた。
「大学への進学率もかなり高いし、受験にはかなり力を入れている。起業家や、有名人も結構でてるんだぞ」
「……ここの学校は野球部がないんですね」
「野球? 河北、部活やりたいのか? ……違うかな、河北が気にしてるのは有原のことか」
パンフレットに目を落としていた智恵は、顔をあげた。先生は疲れた顔でため息をつく。
「有原の成績じゃ、河北と一緒にこの高校に入るのは厳しいだろうな。確かに友達は大切だ。今までは公立学校だったから、良くも悪くもいろんな人間がいるだろ? けど、受験っていうのは自分で学校を選び、学校からも選ばれるんだ。だから、気が合うやつが集まりやすい。俺も、高校の頃知り合った友達とは未だに仲いいしな。だから、河北には今の友人関係を基盤に進路を選んで欲しくない」
「翼は……」
「進路は仲良しの延長で選ぶもんじゃない。高校進学は一生モノの問題なんだから。自分の将来を大事にしろ」
智恵は口をつぐんだ。先生の助言もわかる。志を持つ人が集まる進学校も魅力的だった。けれど、進路だけじゃなく友だちだって一生モノだ。幼稚園からずっと一緒だった翼と、別々の高校に進むことは考えられない。
「本当の友だちなら学校が違っても関係ないだろ。放課後に会えるさ。まあ、ゆっくり考えてみるといい。それから、明日でもいいから有原に進路面談のこと伝えておいてくれるか?」
「わかりました。この後、翼の家にプリント届ける予定なので、その時に言っておきます」
「河北」
「はい」
「後悔しない方を選べよ」
進路相談ファイルを持った先生は、捨て台詞のようにそう言い残すと、教室を出て行った。
◇
進路面談を終えた智恵は、その足で翼の家へ訪れた。お見舞いに秋の花を一輪携えて、二階の窓を見上げる。
「お花だけじゃなくて、何か食べられるものも持って来ればよかったかな……」
「あれ、智恵ちゃん?」
ドアのチャイムを押そうとした時、たまたま家にいたらしい翼のお母さんに声をかけられた。
「翼、元気ですか?」
「大丈夫よ。わざわざ見舞いに来てくれたの? 今翼呼ぶから、あがってって」
お母さんが玄関から「翼、智恵ちゃんきてるよー」と叫ぶと、パジャマ姿の翼がのろのろと二階から顔を出す。
翼は重たげなまぶたを擦り、玄関にいる智恵を迎えた。
「ともっちだー!」
「起こしてごめんね。すぐ帰るよ」
「ともっちの顔見たら元気になったよ」
大丈夫、と翼は笑った。その拍子に、額の冷却シートがぺろりと剥がれた。
翼の部屋の窓辺に、花を生けた花瓶を飾る。壁には「1日素振り200回」と書かれた張り紙が貼ったままになっていた。ベッドサイドにはバットが立てかけてあり、勉強机には教科書ではなく野球ボールが置いてある。外は木枯らしが吹いているのに、この部屋だけがあの夏の熱い試合の日から時間が止まっているようだった。
「わざわざお見舞いにきてくれてありがとう。ともっちは優しいなぁ」
「翼が元気を出してくれるなら、なんでもするよ」
「私ならもう元気だよ。時々咳がでるくらいで」
智恵が持ってきた学校のプリントの中から進路面談のお知らせを見つけた翼は、けだるそうに両腕を上げ体を伸ばした。
「もう受験生だし、勉強がんばんないとー! 明日はきっと学校に行くから。体調もよくなってきてるし」
「先生も、有原もっと勉強頑張れ!って言ってたよ」
「うっ……こないだのテスト、よくなかったんだよね」
「わからないところがあれば、いつでも教えるから言ってね」
「ありがとう……けほっ……」
痛々しく咳き込んだ翼は口元を抑える。
「せっかくだから、ゆっくり休みなよ。今までずっとがんばってきたんだから、きっとどこかで疲れがたまってるんだよ」
「全然疲れてなんかないよ。野球の練習してた時の方が……」
翼は口をつぐんだ。目が宙を泳ぐ。窓から吹き込んだそよ風に押されて、机に置かれたままの野球ボールが静かに転がり床に落ちた。野球ボールは、翼の足元にこつんとぶつかり動きを止める。
「……私、野球してる翼が大好きだよ」
「ともっちは、いつも応援に来てくれたもんね」
翼は足にぶつかった野球ボールを拾い上げることもせずに、ベッドへ腰を下ろす。
「これからだって、応援してるよ」
「ありがとう。じゃあ、がんばらないと!」
何をがんばる気なんだろう。翼はただただ空虚に微笑むだけで、意味のあることは何も言わなかった。
「横になって休みなよ。頭痛いんでしょ? 私はもう帰るから」
立ち上がった智恵の制服の裾を、翼がきゅっと掴んだ。
「もうちょっと話そうよ」
「いいよ。何話す?」
「何か……他愛もない話しよう?」
「じゃあ、最近流行ってる学校七不思議の話でもしよっか。隣町の学校でね……」
「えっ、それって怖い話?」
「違うよ、全然怖くないよ」
「本当かな……?」
怯えた様子で布団を握りしめている翼に、智恵は「本当だよ」と笑いかける。弱っている翼をおいていくことなんて、できなかった。
気づけば時計の針は夕方6時を過ぎていた。
帰り際、リビングでお茶を飲んでいたお母さんと目があう。
「あら、これから帰るとこ?」
「はい。長居してすみませんでした」
「少し日が落ちてきてるし、もう外暗くなるから送っていきましょうか」
「そんな、悪いです」
「いいのよ、気にしないで。そろそろ夕飯の買い物に行こうと思ってたところだから」
翼に見送られながら、お母さんと一緒に家を出る。オレンジと紺色の混ざり合う日暮れの道には、ぽつりぽつりと街灯がつき始めていた。お母さんは智恵を守るように車道側を歩く。
「智恵ちゃんのおかげかな。翼、ちょっと元気でたみたいでよかった。ありがとう」
「翼、家ではどんな感じですか?」
「落ち込んでるみたい。全然喋らないの」
「やっぱり」
「先月までは録画した甲子園の映像とかみて毎日楽しそうにしてたけど、最近は、もう」
「野球をすることが、翼の元気の源でしたもんね」
「まあね。これは失恋みたいなものだから、放っておくしかないのかもしれないわね。甲子園にフラれた傷もそのうち癒えるわよ」
野球の練習や試合が近づくたび、翼は嬉しそうに飛び跳ねていた。だから智恵は、どうしたら翼が大好きな野球をもっと頑張れるだろうかと、そんなことばかり考えていた。お水を持ってってあげたら喜んでくれるかもしれない、もし怪我したらすぐ消毒してあげる、学校の宿題なら手伝うよ、だから翼は思う存分野球に専念していてね。
親友として何年も翼を見守ってきて、誰よりもそばで翼を応援してきたつもりなのに、今、野球を見失った翼をどう励ましたらいいかわからない。何もかも野球のおかげだったのかな。そう思うと「親友」という絆がとても脆く感じた。
黙り込んだ智恵を見て、お母さんが苦笑いした。
「智恵ちゃん、もっと自分のことも大事にしてね。翼のことばっかり考えてたら、智恵ちゃんの青春は翼一色で終わっちゃうわよ? もう受験生なんだし」
お母さんは、冗談めかして智恵の体を肘で小突いた。自分を粗末にしているつもりはない。けれど志望校を考える時、必ず翼の顔が脳裏に浮かんだ。
「受験生かぁ……」
「智恵ちゃん、進路のことで迷ってる?」
「……先生に偏差値の高い高校を受けるように勧められたんですけど、私は翼と同じ高校に行きたくて」
「智恵ちゃんは、どんな高校生活を送りたいの?」
「どんな高校生活……」
「新しい友だちをたくさん作りたいとか、部活に入りたいとか、勉強を頑張って医学部に入りたいとか、いろいろあるじゃない?」
「毎日楽しい学校生活が送れたら、それが一番です」
「それはそうだけど! そう能天気なことも言ってられないわよ?」
「今はあまり高校生活のことまで考えられないんです。ただ、落ち込んでる翼を放って、遠くの高校になんか行けない」
「翼に同情してるの?」
「そんな気持ちじゃないです」
もし翼が元の明るさを取り戻しても、やっぱり別々の高校には行きたくないと思う。元気な時には翼の笑い声を聞いていたいし、調子の悪い時には寄り添っていたかった。
(でも、落ち込んでる翼に何がしてあげられるんだろう。ただ、そばにいるだけなんて……)
役に立てないならいっそ離れたほうがいいんじゃないか、と冷酷な革新案がよぎって、憂鬱になる。
「智恵ちゃん。もし、翼と一緒に高校生活を送りたい、っていうなら、それでもいいと思う。でも、今の翼が心配だから、っていう理由で同じ高校に進学するのはやめたほうがいい。心配事があるならここで吐き出しなさい」
智恵は、車道側を歩くお母さんの顔を見上げる。お母さんになら、なんでも話せてしまいそうだ。
「……翼のもとに届いた手紙なんですけど」
もっと自分にできることがあったんじゃないかと、この手紙を見るたび後悔で胸がじくじく痛んだ。右手に持つカバンがひどく重かった。カバンの奥底にしまったままの薄い手紙のせいだ。カバンを開け、教科書の隙間に埋もれていた手紙を取り出す。
「これが、例のやつね」
「翼が何度も何度も机の中でこれ見返して、悲しそうな顔してるのを見てられなくて」
「こんなのは、こうしちゃえばいいのよ」
お母さんは手の中で紙飛行機を折ると、近くのゴミ捨て場へ手紙を飛ばした。
「わっ……」
紙飛行機はふわふわ宙を揺れながら、ゴミ袋の上に着地する。それに驚いたカラスが数羽飛び立った。お母さんが何の造作もなく手紙を捨てたのを見て、智恵は目を丸くする。
「智恵ちゃんまで気負ってちゃだめよ」
紙飛行機はゴミ捨て場で風にあおられてゆらめいている。手放してしまえば、それはもうただの不要な紙切れだった。
「翼は今、野球から少し離れたいんだと思う。でも、今までずっと野球漬けだったから、忘れる方法もわからないんだと思う。けど、結局自分で納得して先に進むしかないから。智恵ちゃんは自分のやるべきことをやって」
自分のやるべきこと。受験勉強だろうか。あまり気が進まない。
「でも、落ち込んでる翼の気を紛らわすことができるのは、智恵ちゃんだけかもしれないから、今まで通り仲良くしてあげてね。
「それで、元気になってくれますか……?」
「大丈夫。何かきっかけがあれば、また立ち上がる子だから。その時がくるまで、見守っててあげて」
どこか寂しそうに微笑むお母さんを見て、智恵はゆっくりうなずいた。
◇
次の日、学校にやってきた翼はまだ元気がなさそうだった。授業中もずっと上の空で、机に転がる消しゴムを鉛筆で弾いている。ノートをとっている気配もない。昨日まで熱があったせいか、食欲がでないようで昼ごはんを残していた。
放課後の進路面談を終えた翼は、廊下の窓によりかかってグラウンドを見つめていた。まだ体調が万全ではないのか、どこか気だるげだ。
「翼? 何してるの」
「外の風が気持ちいいなぁ〜と思って」
「そうだね、すっかり寒くなったね」
智恵は翼の横に並んで、窓枠に腕をついた。廊下の窓からはグラウンドの様子がよく見える。野球部の後輩が声出しをしながら外周を走っていた。それを目で追っていた翼がつぶやく。
「……もう、十分やったよね」
「翼?」
「昨日、ちょっぴり考えてたんだけど」
「なに?」
翼は窓に背を向けると、智恵の顔を覗き込む。
「野球をやめても、私と友達でいてくれる?」
「ええっ、そんなの当たり前だよ? なんで?」
「野球をしてない自分って、なにもない人間みたいに思えるんだ」
「翼がどんな道に進もうと、私は翼のことが大好きだよ。翼には、いつもやりたいことをやっていて欲しいな」
翼は俯くと、軽く息を吸った。
「私、もうやめるよ。野球」
笑顔で悲痛なことをいう翼を見て、智恵の胸がちくりと痛んだ。あんなに野球が大好きだったのに。やめられるわけなんてないのに。私がもっと役に立てたら、翼にこんなこと言わせずに済んだかもしれないのに。
「高校で、野球やらないの?」
「うん。もうやるだけのことはやったから、未練はないよ。それより、勉強しないと。さっきの進路面談で先生に怒られちゃったよ」
「受験勉強なら、今からでも間に合うよ」
「ともっちは志望校、決めてる? 一緒の高校に行けたらいいね」
翼の屈託無い笑顔が、智恵の胸にすとんと入り込む。翼も智恵も、親友と離れ離れになる未来なんて想像できなかった。私は翼に気を使っているんだろうか、それはお母さんに指摘されたような同情心だろうか。大事な友達と、ずっと一緒にいたい。それだけの気持ちで将来も生きていけたらいいのに、進路問題はそう生易しくはなかった。
「まだ、決めてないんだ」
「そうなんだ、私もまだ決めてないけど、ともっちと同じ高校行くには勉強しないといけないといけないね」
「今の翼の成績だと、ここからもっとがんばらないと!」
「うっ……そうだよね。これから猛勉強するよ! だからともっち、私に勉強教えて欲しいな」
「もちろんだよ。がんばろ〜!」
同じ学校を受験したとして、もし仮にどちらか片方だけが不合格だったら。そんな不安を振り払いながら、二人は勉強するために近くの図書館に向かった。
受験生の溜まり場となっている図書館で、隣合わせで座り参考書を開く。
「私、数学苦手なんだ。関数とか反比例とか、苦手……」
「じゃあ、まずは比例と反比例からやろう」
弱音を吐く翼に、智恵が一から丁寧に手ほどきをした。比例反比例、その次は関数。それから英語の疑問文の作り方や現在完了形。教科書を広げながら次々と解説を終え、練習問題に取り掛かる。
過去問を解いていた智恵は手を止めた。
うんうんと唸りながら問題を解いていた翼が、黙り込んだままぴくりとも動かない。
「……翼?」
翼は瞳を閉じて、参考書を枕に安らかな寝息を立てていた。人差し指で頬をつつくと、安らかな寝息が手の甲をかすめる。
「……もう」
智恵はあきれながら、自分のカーディガンを翼の肩にかけた。それから携帯を取り出すと、レンズを翼の顔に近づける。パシャ、と小さなシャッター音が鳴った。翼の情けない寝顔を撮った智恵は、翼が起きたら見せてあげよう、とほくそ笑む。
今までに携帯で撮った写真を見返していると、暑い夏の日に撮った一枚を見つけた。
ユニフォームを着た翼が、逆転ホームランを放った日に撮った一枚だ。
中学校生活最後の公式戦は最高の舞台だった。翼の放ったホームランが大きな弧を描いて大空へ飛んで行ったこと、笑顔でピースしてくれたこと、自信満々に駆ける背中と、太陽に焼かれて光る白いユニフォームが眩しかったこと、額を伝う汗の一滴一滴が、夏の神様からの贈り物みたいに尊く見えたこと。
「翼、がんばれーっ」
あらんかぎりの力で叫んだ声すら、大きな歓声に飲み込まれて消えてしまう。自分が燃え盛る球場の一部になれたようで、なんだか気持ち良かった。
まぶたを閉じればあの日に見たすべてのものが、球場のざわめきや土煙のにおいを伴って鮮明に蘇る。
優勝を飾った見事な一戦。そして試合後に、ぽつねんと立ち尽くす翼の小さな後ろ姿。
「……私が今までやってきた野球って、なんだったんだろう」
優勝後、どのスカウトマンからも声をかけられずに一人ぼっちでいた翼。その口から無意識に溢れた言葉を智恵は聞き逃さなかった。
「翼……」
あのきらめきが一夏限りで終わりだなんて、私は全然信じていないよ。
携帯の画面を伏せて机に置く。
智恵は、隣で居眠りしている翼を見つめた。野球を諦められないのは、翼だけじゃない。智恵も、あの日のことが忘れられなかった。もしもまた、グラウンドを走る翼をそばで観れたなら。そんな翼の支えになれたなら。
後悔しない方を選びなさい。
先生の助言が蘇った。それなら、偏差値で決まる未来より翼との将来にすべて賭けたい。
彼女はもう野球を止めるといっていた。もしもその宣言通り、翼が二度と打席に立たなかったら……。
智恵は、眠っている翼の前髪へ指を伸ばした。
翼がどんな結論を出しても、私は見守り続けると決めたんだ。
そして、閉じた瞼にかかる翼の前髪を優しくかきあげる。翼はどんな夢を見ているんだろう、と思いを馳せながら、幸せそうな寝息に耳を傾けていた。