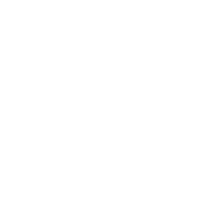第10話 九十九 伽奈「秋雨の日」
『友達が欲しい、って思います』
そう書かれたメモ書きを見つけたのは、秋雨の降る夕方のことだ。
伽奈には、昔から欲しいものが何もなかった。
クリスマスプレゼントは何がいい? 誕生日には何が欲しい? 時期が来ると大人たちから浴びせられるそれらの質問に「あなたが選んでくれるものなら、なんでも嬉しいですよ」と答え続けていたら「なんてよくできた子」と必ず褒められた。けれど伽奈には、何がどうしてよくできているのか、さっぱりわからない。ただ、物欲が欠けているだけなのに。欲しいものがある人のほうが、よっぽど「できた子」なんじゃないかとさえ思う。
◇
『今回も、よくできましたね』
放課後に返却された英語の小テストは満点だった。その脇に、先生からのメッセージが書かれている。
私がよくできること。勉強と運動。あとはなんだろう。じゃあ、この先できるようになりたいことは?
「九十九さん!」
同じクラスの笹野さんに声をかけられて、伽奈は顔をあげた。
「練習、いくよ」
そう誘われて、席を立つ。
放課後の校舎は、部活動に向かう生徒たちで活気づく。笹野さんは空き教室の扉を開けた。そこでは演劇部の部員たちが発声練習や、柔軟体操、腹筋などに励んでいる。
伽奈が部室に入ると部長が素早く駆け寄ってきて、伽奈の手を両手でしっかりと握った。
「九十九さん、今日もよろしくね」
伽奈は帰宅部だ。けれど今回の公演に限って、部長に頼まれ演劇部の手伝いをすることになっていた。いつも男役を担当している部員が成績不振のため部活にでられず、代役を探していたらしい。
「ああ、もう本当に助かるわ。あなたがいてくれて。立っているだけで絵になる役者っていうのはね、本当に重宝するんだから。ああ、もし何か不安なこととか困ったこととかあったらいつでも私に相談してね! 同じクラスの笹野さんの方が話しやすいなら、笹野さんにでも!!」
部長は滑舌良く早口でまくし立てた後、両手をパン、と叩いて集合をかけた。
「それじゃ、あと10分したら台本の読み合わせはじめましょう!」
今回の演劇部の台本は副部長が書き下ろしたオリジナルストーリーだ。ただし、シェイクスピアを現代風にアレンジした要素が多く含まれていて、過去の様々な戯曲が下地になっているらしい。伽奈に与えられた役は、「孤高のイケメンだけど貧乏な若者」というポジションだった。セリフは多くないものの、たくさんの女性から求婚されて物語の中で重要な役割を担っている。
大道具や美術担当の生徒は教室の後ろや廊下を使って作業に勤しんでいた。みんなの熱気があふれているせいか、窓を開けていても教室は蒸し暑い。
伽奈は、もらったばかりの台本をめくり、自分のセリフに目を通す。
「あ、九十九先輩だよ」
「ほんとに舞台でるんだ。かっこいいなぁ。男役、絶対似合うよ」
廊下から、女の子たちがひそひそと騒ぐ声が漏れ聞こえた。伽奈は振り向くこともせず、黙々と台本のページをめくる。
「嬉しいの? ああやって、キャーキャー言われるのって」
笹野さんはそう囁くと、廊下でたむろしている女の子たちへ冷めた視線を送る。たいして話すこともないだろうに、彼女たちは伽奈を見て盛り上がっているらしい。
「特に気になりません。それより今は台本を覚えるので精一杯ですから」
「そう。芝居はどう?」
「みなさんの熱意に圧倒されそうです。これだけの人数がいて、誰一人怠ける人がいないのはすごいことですよ」
ふーん、と興味のなさそうな相槌を返しながら、笹野さんは目を逸らした。
「……九十九さんって、何を考えているのかわからない」
台本をめくろうとしていた伽奈の手がとまる。わからないのはこっちの方だ。この教室や学校にいる彼ら彼女らが何を考えているのか。どうしてここまで演劇や部活に打ち込めるのか、授業をサボリたがるのか、容姿の優れた人をみると騒ぐのか。
それだけじゃない。実のところは、自分が何を考えているのかだって、よくわからなかった。何がしたいのか、何が欲しいのか、何か欲しがらないといけないのか。言及したところで意味のない問いを繰り返すはめになりそうだ。だからこそ、効率的できちんと結果のついてくる勉学や運動にひたすら打ち込んでいたい。
「今は、このお芝居のことを考えてますよ」
やりたいことがないからこそ、人から頼まれたことにはできる範囲で応えることにしている。今回、演劇部の助っ人に参加することにしたのも、そのためだ。
「そうじゃなくて……」
笹野さんが何か言いかけた時、部長が二回手を叩いた。読み合わせの時間だ。
「さあ! そろそろ10分経ったわね。セリフはちゃんと頭に入った? それじゃ、始めましょう」
笹野さんは黙って伽奈のそばを離れていった。伽奈は静かに台本を閉じる。
(何を考えてるかわからない、か)
笹野さんのさめざめとした声色が、何故だか耳に焼きついて離れなかった。
◇
演劇部の練習を終えた後、戯曲や芝居に関する知識がまるでない伽奈は町の図書館を訪れた。助っ人として入る以上、手抜き仕事はできない。まずはシェイクスピアから制覇しようと、英文学の棚を訪れた時だった。
『夏の夜の夢』
タイトルに惹かれて本の背表紙に指をかける。ゆっくり本を引っ張り出すと、ページの隙間から小さな紙切れが落ちた。
そこには誰に宛てられたものでもない、秘密の日記帳にしか書けないようなメッセージが書かれていた。
『本を読んでばかりの毎日です。読書は楽しいし、幸せだけど』
わずかに丸みのある優しい文字だ。折りたたまれていた用紙のシワを指先で伸ばす。そのメッセージの最後の一文はこんな言葉で締めくくられていた。
『やっぱり、友達が欲しいって思います』
伽奈は紙片を折りたたんだ。驚いた。自分が思っていることを、こんなに赤裸々に言葉にできるものなのか。顔や名前はわからなくても、手書きの文字を読んでいると、真剣に思い悩んでいる彼女のことがとても近しい存在のように感じた。
(友達が欲しい、なんて)
私は今まで、こんなふうに思ったことがあっただろうか。手紙の主のまっすぐな気持ちが、なんだか羨ましかった。
伽奈はカバンからノートを取り出すと、さらさらと返事を書いてページを破った。四つ折りにたたんで、本の同じページに挟み、本棚に戻す。
それはただの気まぐれだった。だから、彼女とのやりとりもその一度きりで終わると思っていた。
『まさかお返事がいただけると思っていなかったので驚きました』
数日後、再び図書館を訪れた伽奈は、同じ本に挟まっていた新たなメモ書きを手にして、目を見開いた。
今度は自分に宛てて書かれたメモ書きを読み終え、カバンからメモ帳を取り出す。
返事をする義務はない。名前も素性もわからない相手に届く確信もない。けれど、彼女の話をもっと聞きたいと思った。彼女が書く文字の、やけに整った筆跡や、ぴったり角を揃えておられた便箋の感じがなんとなく心地良い。
そして、顔も名前もわからない彼女と手紙を交換するのが、伽奈の新しい日課になった。毎晩、自習を終えた後に丁寧に返事を書いた。最初は短かった手紙の内容も、回を重ねるごとにどんどん長文になっていく。
次第に、ノートの切れ端ではなく文房具屋で購入した便箋で手紙を書くようになった。受け取った手紙の数も増え、それを保管していたクリアファイルはだんだん分厚くなる。
『あなたも困ったことがあったら、いつでも相談してくださいね。私でよければいつでもお聞きします。お力にはなれないかもしれませんが……』
その日届いた彼女からのメッセージの後ろには、そんな一文が添えられていた。困ったこと。何かあるだろうか。彼女は自分にどんなことでも打ち明けてくれる。伽奈はそれを聞いたり解決策を一緒に考えたりすることはできても、自分の悩みを語ることはできなかった。
悩んでいること、困っていること。ないといえば嘘になるけれど、はっきり言葉にすることはできなかった。ましてや誰かに話すことなんて、もっと難しい。
ボールペンを手の中で回しながら、白紙の便箋と向き合った。
(そうだ、合唱コンクールの話でも書こうか)
伽奈は先日あった合唱コンクールのことを思い浮かべた。学年別、クラス対抗の合唱コンクールは例年盛り上がる恒例行事の一つだ。
「優勝だよ! やったね!」
合唱コンクールで優勝した瞬間、クラスメイトたちは笑ったり泣きじゃくったりしながら伽奈に抱きついてきた。
「そうだね、私たちが一位だ」
伽奈は彼女らに調子を合わせて優しく肩を叩き、慰める。自分もみんなと同じように、毎日練習に打ち込んだはずなのに、みんなのようには泣けなかった。
目を真っ赤に腫らして嬉し泣きするクラスメイトを慰めるとき、ふと胸に小さな不安がよぎった。自分は本当に、彼ら彼女らと同じ世界を見ているんだろうかと。
(あの日に自分が感じたこと、この子ならわかってくれるかもしれない)
伽奈は文通相手がくれた手紙の束を眺める。この子は合唱コンクールや体育祭で泣いたり笑ったりするタイプの女の子なんだろうか。
「……やっぱり、書けないな。こんなこと」
伽奈はペンを置いてため息をつく。それから、演劇部の助っ人としてがんばっていることなんかを当たり障りなくすらすら書いて、便箋をたたむ。
◇
(何か、おかしい)
その日、部室の扉に手をかけた伽奈は一瞬、入るのをためらった。いつもなら廊下で作業する大道具担当の部員や、筋トレに励む役者たちで騒がしいはずなのに、今日はえらく静かだった。
そろそろと扉を開けて部室に入ると、みんなの視線が伽奈に集まる。
「何かあったんですか?」
「……九十九さんにも、ちゃんと説明しないといけないわね」
いつになく厳しい顔をした部長がロッカーを開けた。畳のような渋いにおいが鼻をつく。
「今回、ヒロイン役をやる部員の衣装に墨汁がかけられていたの。それで、隣に置いてあった九十九さんの衣装も汚れちゃって……」
教室の床には墨汁の後が残っていた。ヒロイン役の女の子は、汚れた衣装を洗いに洗面所へ行っているらしい。
伽奈の衣装は、今回汚された衣装の下にあったため、比較的軽い被害で済んだものの、真っ白だったジャケットにはあちこちに灰色の丸いシミがついていた。
「あ……」
「ごめんなさい。これから部員だけで会議するから、九十九さんはもう帰っていいから……部内のみっともない問題に巻き込んで、申し訳ない」
部長が深々と頭を下げた。伽奈は、いえ……と首を振る。あまり深入りするのもよくないだろうから、と踵を返し部室を出ようとした時だった。
「ねえ」
笹野さんが、伽奈を呼び止める。
「怒らないの?」
「え?」
「あなたは、もっと怒ったほうがいいよ。泣くんでもいいし、あざ笑うでもいいけど。ねえ」
笹野さんのまっすぐな目が伽奈をとらえた。充血して赤みがかっている目は、どことなく怒っているようにも、悲しんでいるようにも見える。
怒った方がいい、なんて言われたのは初めてだった。どういうこと? と聞き返したかったけれど、火に油を注ぐような気がして、躊躇ってしまう。
「笹野さん、九十九さんを困らせても仕方ないでしょ」
伽奈が言葉に詰まっていると、部長がそう制止をかけた。そして伽奈は、どこか後味の悪いまま、一人で帰路に着いた。
その日は雨が降っていた。道行く人々の顔が傘で隠れている。大きな傘を広げて歩く人々で埋め尽くされ、いつもより道が狭い。
足早に歩くサラリーマンがまっすぐに突進してきた。伽奈は傘を軽く傾げた。それなのに、サラリーマンは大きく舌打ちをすると、灰色の傘を伽奈の傘にぶつけて去っていく。
(わ……)
伽奈は飛び散った雨つぶで汚れた足元を見つめる。家に帰ったら洗わないと。風邪をひかないようにしないと。頭に浮かんでくるのはそういった解決策と、冷たい雨の温度感ばかりだ。
『怒った方がいいよ』
笹野さんの言葉が蘇った。今まで一度も怒ったことがないわけではないはずだ。けれど、いつどんな時、なぜ自分が怒ったのか思い出せなかった。やっぱり自分は、今までに一度も怒ったことがないのだろうか。じゃあ泣いたことは? あくびをした時と、玉ねぎを切った時に涙がでた。けれど笹野さんのいう「泣く」はそういう生理現象とは違うだろう。じゃあ自分はまだ、本当の意味で泣いたことがないんだろうか?
「……なんでここに」
考え事をしながら歩いていたら、知らない間に図書館についていた。まっすぐ家に帰るつもりでいたはずなのに。かすかに戸惑いながら、傘をたたんで図書館の門をくぐった。
イギリス文学を扱っている棚は、理系の本と違って装幀の凝っている本が多かった。奥の本棚からただよう埃っぽいにおいにももう慣れた。いつもの癖で『夏の夜の夢』を引っ張り出すと、そこにはすでに彼女からの返事が差し込まれていた。しっかり折りたたまれた便箋を開く。
『今日はあなたに相談したいことがあるんです』
なんだろう。伽奈は素早く手紙へ目を通した。
『クラスメイトに「遊びに行かない?」ってさそわれてしまいました』
よほど嬉しかったのか、いつもより文字が乱れている。
『別にみんな私と友達になりたいから誘ってくれた、ってわけじゃないんです。
数合わせとして誘われただけなのに、こんなに緊張してバカみたい、さらっと断っちゃいなよ、って思う自分と、これを機にみんなで仲良くなれるかもしれないんだから行って来なよ、って思う自分がいます』
今日届いた手紙もまた、思ったことをありのままに綴った素直な文章だった。
他人の頭の中も、自分の頭の中もはっきりとは見えない。けれど、この子のことだけは、よくわかる。手紙を読んでいると、妙な安心感に包まれた。
椅子の背に持たれていると、電話が鳴る。兄からだ。図書館にいた伽奈は慌てて外に出ると電話を掛け直した。
「どうしたの?」
「明後日の夜、外でご飯食べることになったんだけど早く帰ってこれる?」
「大丈夫」
伽奈の両親は医者で、兄も医学部に通っている。仕事や勉強で忙しくしている家族が揃う日は稀で、外食に行くのも久しぶりだった。仕事終わりの父と母は少し疲れているようだったけれど、食欲は旺盛だ。レストランのテーブルにはピザやパスタ、牛肉を乗せた大皿が並ぶ。
「伽奈、演劇部の手伝いしてるんだって?」
食事中、唐突に兄が切り出した。ちょうどピザにかじりついたところだった伽奈は、無言で頷く。
「あなたもお人好しね。陸上部のお手伝いとかバスケ部のお手伝いもしてなかった?」
母が、ナプキンで口をぬぐいながら伽奈を見つめる。
「……いろんなことを経験できて、いい勉強になるから」
「それもそうね。そういえば最近、お芝居なんて全然見に行ってないわ。昔は好きでよく行ってたんだけど。伽奈が手伝ってる芝居、見てみたいわ」
「公演は平日だし、無理だよ」
母は少し残念そうに眉をひそめ、父は短く、そうか、とつぶやいた。
『公演のチケット、二枚あげる。友達でも家族でも、誰でも好きな人を招待してちょうだい』
数日前、演劇部の部長からそう言われたばかりだった。そのチケットは封筒に入ったまま、机の引き出しで眠っている。
家族との外食を終えた伽奈は、帰宅すると学習机の前についた。寝る前の日課である自習を終えると、あの子からもらった手紙の束を取り出す。学校のプリントや宿題の整理なら得意だけど、人から受け取った手紙を片付けるのは苦手だった。かさばるからといって捨てていいのか、いつも迷う。悩みながら、手紙の文面を読み返していると、とある一行が目にとまった。
『舞台に立つあなたの姿はきっと素敵なんだと思います。演劇、がんばってくださいね』
手紙に書かれた彼女の言葉だけは、すとんと胸に落ちてきて、伽奈の心の栄養になる。
伽奈は机の引き出しを開ける。演劇部の招待チケットが入った封筒を取り出した。よかったら見に来てくれませんか。そう誘ってみようか。彼女は、自分と直接会うことは望んでいないのかもしれない。けれど。
伽奈は椅子にもたれかかると、部屋の天井を見上げた。
(受け身でいるばっかりじゃ、だめだ)
彼女と、直接会ってみたい。
そう決意を固めた次の日から、運悪く演劇部の練習時間が長くなってしまった。公演日が近づいたせいだ。練習が終わる時間は図書館の閉館時間を過ぎる頃で、なかなか足を運べない日が続いた。
練習が休みになった金曜日。久しぶりに図書館を訪れ、足早に英文学の棚に向かう。
『お茶でもしませんか』
本の隙間には、彼女からのお誘いの便りが挟まれていた。今度こそ自分から声をかけるつもりでいたのに、結局、彼女に先を越されてしまった。伽奈は苦笑しながら、時間をかけて返事をしたためる。
『私も、あなたと会って話してみたいと思ってました。友達になれたら嬉しいです。 九十九伽奈』
そのメモ書きを挟んでから数日は、どこか足元のあたりがそわそわして落ち着かなかった。練習があって図書館に行けない日もあったけれど、時間がある日はなるべく足を運んだ。
けれど、一週間たっても彼女からの返事が届くことはなかった。
◇
「九十九さん、怒ってる?」
演劇部の練習中、笹野さんが伽奈の顔を覗き込んだ。思わず肩がぴくりと揺れる。
違う、怒ってるわけじゃない。やんわり否定すると、笹野さんは例によって、冷めた口調で「ふーん」と答えた。伽奈は目を逸らし、教室の窓へ目をやる。
怒りとは違う、悲しみともきっと違う。
「少し、水を飲んできます」
伽奈は席を立ち、部室を後にした。水飲み場の電気をつけると、蛇口に口を近づける。胸にぽっかり空いた空白。お腹が空いてるわけでもないのに、妙な空腹感が消えない。頭を冷やそうと、そのまま蛇口で顔を洗う。両手で頬を軽く叩き、顔を上げた。
鏡に、びしょ濡れになった自分の顔が映る。大きな水滴が頬を伝って、顎から落ちた。まるで泣いているみたいだ。
伽奈は、ふっとため息をもらすと、洗い立てのタオルに顔を埋めた。