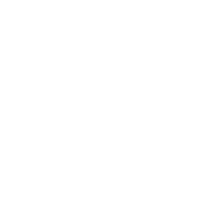第11話 初瀬 麻里安「名のない手紙」
薄い水色の便箋を折りたたんだ。封筒には宛名がない。差出人の名前もない。住所もなければ切手もない。それでも手紙は、きちんと相手の手元に届いた。
返事はいつ頃になるだろう、とわくわくしながら、今日も麻里安は手紙を出しに行く。
顔も名前も知らない彼との文通が始まったのは、夏の終わりの頃だった。
◇
−−−−初瀬さんっていつも一人で本読んでるよね。
漏れ聞こえてきたクラスメイトの会話に、麻里安は唇の端をきゅっと結んだ。本を持つ手に力が入る。休み時間、大抵のクラスメイトは友達同士で集まって噂話や他愛もないおしゃべりに興じている。麻里安が黙々と本を読んでいるのは、友達がいないからじゃない。
(好きでこうしてるだけですから……)
次のページをめくる。物語はもうクライマックスだ。目で活字を追いかける。けれど視界の片隅にちらつくクラスメイトの姿が気になって、いつものように物語に没入できなかった。
図書室が恋しいと思った。人の気配がする教室より、本のにおいがする図書室の方が気が安らぐ。
(「人間嫌い」っていうわけじゃないんですけど……)
本を閉じた。クラスメイトが机を叩きながら笑っている。もうすうぐ6限目が始まる。それが終われば、放課後だ。
学校の図書室は、ここしばらく閉館中だった。古書の入れ替え中で、貸し出しができないらしい。図書室がある東側の廊下は西側に比べると静かだ。西側の廊下は部活生であふれていていつも騒がしい。特に夏は、日焼け止めと制汗剤のむせかえるようなにおいが漂っている。だから麻里安は図書室に用事がない時でも東側の廊下を使っていた。
図書室の前を素通りして階段をおりると、保健室の前で足を止める。
『相談ポスト 人に言えないお悩みを投函してくださいね』
保健室の前に小さなポストが設置されていた。ポストに投函されたお悩みには、すべて保健室の先生が返事を書いてくれるらしい。
(人に言えないお悩みなんて……)
麻里安はポストをじっと見つめた。
保健室の前でたたずむ麻里安のすぐそばを、同じクラスの女子たちが通り過ぎていく。
「身長測ってこーよ」
「体重はー?」
「人に見せらんないよ! 極秘だから!」
彼女たちは楽しそうに笑い合いながら保健室になだれ込んだ。保健の先生が『相談ポスト』を考えたのは、保健室が病人や悩みを持つ生徒の居場所ではなく、ガールズトークをするための場所になりつつあるからだろう。
麻里安は腕に抱えた本をぎゅっと抱きしめると、相談ポストの前を立ち去った。放課後の空き教室も、保健室も、玄関ロビーも、どこもかしこも誰かの溜まり場になっている。麻里安が唯一安心していられる場所といえば、近所の図書館だけだった。
◇
図書館の窓は開けっ放しになっていて、外の雨音が館内によく響いた。夕立ちが降っている。図書館の隅で読書に没頭していた麻里安は本を閉じた。最近はハリーポッターの影響で、イギリス文学にハマっている。机に積み重ねた本を見つめながら、ハリーポッターに出てくるヒロイン、ハーマイオニーが羨ましいと思った。読書漬けの毎日を送っていても、ハリーやロンみたいに明るくて元気な友達がいるなんて。
窓の外へ目をやる。まだ雨は止まない。制服姿の女の子たちが相合傘をして帰っていく。女の子同士で一つの傘に隠れる生徒もいれば、男女で寄り添っている生徒もいる。
麻里安は相合傘で帰る仲の良さそうな二人の女の子を見つめながら、心の中で勝手にアフレコを始めてみる。
−−−−そっちの方が濡れてるよ。
−−−−私はこのくらいの雨平気だから。
−−−−いやいや。
−−−−あっ、だめだよ。肩に雨当たってるよ?
……そんな風に互いを気遣っているせいで、傘は静かに左右に揺れ続けたりするんだ。
(私も、いつか、そういうことしてみたいです……)
相合傘の下ではしゃぐ女の子のスカートがふわりと揺れる。雨で汚れている白い靴下が、麻里安の目には眩しく見えた。
麻里安はカバンの中から白い便箋を取り出した。『相談ポスト』の脇に置いてあったものだ。便箋の頭にペンを押し付けると、じわりと青いシミができる。
(……何か、書くだけ。書くだけ、書いてみるものいいかもしれませんね……)
青いペンのインクにのせて、胸の内にあるものを吐き出していく。
『本を読んでばかりの毎日です。読書は楽しいし、幸せだけど、やっぱり友達同士で帰宅したり、お弁当を食べているのを見たりすると、ちょっぴりうらやましいなって思います……』
何を書いてるんだろう。あまりにも幼稚すぎる悩みだと思った。けれど、一度書き出してみると、手が止まらなかった。こんなことを思うのは今日限りだから、書き終えてしまえばきっとすっきりするはずだから。そう考えると、筆を持つ手がさらさら動く。
(……私、こんなこと考えてたんだ)
麻里安は自分が書き終えた手紙を見て赤面した。それは誰にも見せられない内容だった。思っている以上に、自分は友情の青春物語に憧れているのかもしれない。便箋を折りたたむ。窓を見上げると、すっかり雨は止んでいた。麻里安は手紙をカバンの底に投げ入れると、数冊の本を詰め込んで図書室を後にする。
夏の夕空には大きな入道雲が浮かんでいた。
◇
その夜、図書館から借りてきた本を読もうとカバンを開けた。ついでに、あの恥ずかしい手紙も処分しようとカバンをひっくり返す。
「あっ、あれ……?」
教科書の隙間やポケットの中。どこを探しても、あの手紙が見つからない。もしかして……と麻里安は青ざめながら、図書館で、帰り際に返却した本のことを思い返した。本の隙間に手紙が挟まったまま、返却ボックスにいれてしまったのかもしれない。
(もしそうだったら……)
麻里安は羞恥心にかられて、ベッドの上で両足をばたばたさせた。誰かに見つかる前に取り戻してこないと、と決意を固め、そわそわしながら布団へ潜り込んだ。
◇
放課後、すぐさま図書館に向かった麻里安は昨日返却した本を探した。ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』。しおりひとつ挟まっていない。同じくイギリス文学の棚に並んでいた『蠅の王』。それも外れだった。昨日返却した最後の一冊、シェイクスピアの『夏の夜の夢』をめくると、隙間から一枚の便箋が落ちた。やっぱり本の隙間に挟まってたんだ、と麻里安はほっと息をつきながら便箋を広げる。
冒頭に目を通した麻里安は息を飲んだ。見つけた手紙は麻里安が書いたものではなかったからだ。
『友達が欲しい、と思うのは素敵なことですよ。私も心を許せる友達は多くありませんが、特別作ろうと努力する気になれません。だから、いつか親友が、って希望を抱いてるあなたの心持ちが眩しい。きっとできますよ、友達。大丈夫です』
それは麻里安の書いた手紙への返信だった。黒いボールペンでさらさらと書かれた細い筆致はとても大人びて見える。どこの誰だろう。どんな人だろう。わざわざ返事を書いてくれた相手のことを想像すると胸が高鳴った。きれいな字を書く人はきっと心もきれいなんだと思う。
麻里安は少し考えてから、カバンからノートを取り出すと、その場で返事を書き始めた。
『まさかお返事がいただけると思っていなかったので驚きました。誰にも言えないことを吐き出して、やっぱり誰にも見せられないから捨てるべき……と思っていた手紙だったので、思いがけない展開になって恥ずかしいやら、嬉しいやらです。ちょっと恥ずかしいですけど、小説を読んでてふいに友情に憧れることってありませんか。ワトソンにとってのシャーロックホームズみたいな人が私にもいたらいいのに、なんて。あなたは普段、どんな本を読んでいるんですか?』
そう書いた便箋を折りたたむと、『夏の夜の夢』の隙間に挟んで、本棚の同じ場所へ戻した。シェイクスピアの名作とはいえ、貸し出しの多い人気の図書ではない。この本を通じて知らない相手と繋がったことが、新しい物語の一ページのようで胸が弾んだ。
それから三日後、麻里安はまた図書館のイギリス文学の棚を訪れた。『夏の夜の夢』をめくると、ページにまた便箋が挟まっている。
『友達に憧れる気持ち。なくはないけど、そこまでですね。いたらいいし、いなくてもいい、くらいのものです。私は何に対しても欲が薄いんだと思います。だから、「あれが欲しい」とか「こうなりたい」って前向きに考えてる人を見ると、いいなって思いますよ。
この本を見つけたのはたまたまで、手紙が挟まってるのを見つけた時は驚きました。普段は医学の不思議とか、サイエンス系の本を読むことが多くて、こういう戯曲には詳しくないんです。実は今、演劇部の手伝いをしてて。私は演劇部じゃないんだけど、どうしても男役が欲しいっていわれて、仕方なく。その演目が現代風にアレンジしたシェイクスピアだったので、なんとなくここの本棚を探してました。そしたらあなたの手紙をみつけたんです』
男役。頬に熱が集まる。男の子なんだ。繊細な字を書いて、シェイクスピアを手に取る男の子。サイエンス系の本を読む知的な理系男子。きっと素敵な人なんだろうな、と妄想が広がる。休みの日は何をしてるんだろう、学校はどこだろう、どんな顔をしているんだろう、名前は、年は。気になるのなら連絡先を聞いて毎日やり取りすればいい。それから顔を合わせればいい。その方がずっと効率的だけど、でも。
もっともっと知りたい気持ちが募る一方で、このままにしておきたい気持ちも同じくらいに強かった。
どこの誰かわからない、だからこそ話せることもある。私と彼を引き合わせてくれるのは『夏の夜の夢』というただ一冊の本だけ。
(その方が、いいですよね)
麻里安は、この手紙がどうか彼の目に留まりますように、と願いながら便箋を折る。そして、返事が届くのはいつになるだろうかと思いを馳せた。
◇
教室で手紙を見返していた麻里安は高揚する気持ちを抑えながら、文房具屋で選んだ白地に青い鳥が描いてある綺麗な便箋に筆を走らせた。休み時間の騒がしさも気にならない。
私にもこの世界のどこかに大切な人がいるんです。胸にその淡い秘密を抱えているだけで、こんなにも心強い。
彼とは、あれから何通も手紙のやり取りを交わした。学校のことや家のこと、最近好きな本のこと。一通手紙を受け取るたびに、少しずつ彼に詳しくなっていく。
手紙の続きに何を書こうかと、行き詰まった麻里安はペンの頭を頬に当てる。
教壇の前で女の子たちが旅行の計画を立てている。黒板にチョークで落書きをしながら大げさに手を叩いて笑い合っていた。
「ここ、五人だと入園料が安くなるんだけどなー」
「五人!? あと一人かー……」
「……あっ」
たまたま黒板の方を見ていた麻里安は、女子グループの一人と目があってしまった。慌てて目をそらすのも失礼だろうと、麻里安は気を使って軽く頭を下げた。
すると、女子グループの一人がぽつりとつぶやく。
「初瀬さんも来る?」
「えっ、ええっ!?」
突然の誘いに驚いた麻里安は、ずれたメガネのフレームを慌てて元に戻した。
「こういうテーマパークとか興味ない? きらっきらの夢の国。楽しいよ〜。どうかな、来ない? 来る?」
「あっ……」
彼女は、麻里安の机に手をついて微笑みかける。彼女の押しの強さにたじろぎながら、麻里安はもう一度メガネのフレームを軽く持ち上げた。平静さを装おうとしても、背筋には冷や汗が一滴、静かに流れていった。
◇
『演劇部の練習、調子はどうですか。人前で演技できるなんて本当にすごいです。別世界の出来事みたいです。戯曲はよく読むので、そういうのを読んでるときは、もし自分が『ハムレット』のオフィーリアだったら……とか、妄想してなりきったりするのは好きなんですけど、実際に演じるなんてとても無理です。
そういえば、今日はあなたに相談したいことがあるんです。クラスメイトに「遊びに行かない?」ってさそわれてしまいました。しかも、行き先は千葉にある夢の国ですよ。もう、小旅行ですよね……! そこまで親しくない人たちと遠出できるのか不安です。修学旅行と違って、引率の先生もいませんし……。
それに、私はわかってるんです。誘われたのは、単なる数合わせにすぎないって。なんでも、五人で入ると入園料が安くなるキャンペーンをやってるんだそうです。それで、たまたま私が声をかけられただけで、別にみんな私と友達になりたいから誘ってくれた、ってわけじゃないんです。
数合わせとして誘われただけなのに、こんなに緊張してバカみたい、さらっと断っちゃいなよ、って思う自分と、これを機にみんなで仲良くなれるかもしれないんだから行って来なよ、って思う自分がいます』
宛名のない手紙は、それでも必ず彼のもとに届いた。埃っぽいイギリス文学の棚にある『夏の夜の夢』は二人だけの郵便受けだった。
彼からの返事は、すぐに戻ってきた。
『迷うことない。行ってくるのがいいと思いますよ。きっといい思い出になります。どんな理由で誘われたって、いいじゃないですか。当日おもいきり楽しんで、みんなと仲良くなれれば、それで。めいっぱい満喫してきてくださいね。夏はまだまだこれからですから』
◇
その日はからりと晴れて、青空が広がっていた。
早く待ち合わせ場所についた麻里安は、カバンに忍ばせた文庫本のヘルマン・ヘッセを読みながらみんなが到着するのを待つ。
「初瀬さーん!」
クラスメイトが元気よく手を振りながら、小走りに麻里安の元へ向かってきた。
「もう、ここではね、本読む時間はないからね!」
そして、麻里安が読んでいた本を没収すると、背中をぽん、と軽く押した。
「みんなももうすぐ来るって。さきにチケット売り場行こう!」
女の子五人で夢の国のゲートをくぐる。どこからか漂ってくる甘いチュロスの香りに、銀色の風船を持って駆ける子ども。外国の街並みみたいにカラフルな道路の真ん中を、五人で横並びに歩く。まるで物語の登場人物になったみたいだった。
「何する? 初瀬さん絶叫系いける?」
「そういうのは、あまり経験がなくて……」
「いこいこ! 楽しいから! 物は試しだから!」
「えっ、ええっ!?」
首からポップコーンをぶら下げた麻里安は、誘われるままに次々とアトラクションに乗り込んだ。高いところから急激に落下するときには、五人揃って両手をあげて大絶叫。ふらつく足で乗り物から降りると、また次のエリアに向かう。手足はくたくたなのに、心はずっと高揚したままで、「あっちにも違う乗り物あるよ」と言われると、好奇心が抑えられなくなる。
「初瀬さん、意外といけるね〜、いいね!」
「で、でもすごい怖かったです」
「それがいいんじゃん、怖いのが。わたしだって怖いけど、ちょー楽しいよ。ねっ?」
ねっ? と笑いかけられた麻里安は、呆然としながら、こくりと頷く。そうかもしれない、と思った。怖いけど、楽しい。友達を作ろうとするのも、遊びに行くのも、どこか不安で怖かった。考えるだけで胸が苦しくなるから、いっそ目をつぶっていたいと思った。けれど、そうしていたらここには来られなかったんだ。
瞬きをすると、顔も名前も知らない彼の、流麗な筆跡を思い出した。『夏の夜の夢』の隙間にいつもお返事を書いてくれる彼。今日の出来事は真っ先に彼に報告しよう。
「ほら、行こう。腕組んで歩こうよ〜」
「なんでだよ!」
「いいじゃん、みんなで腕組もう〜! 早く行こ!」
クラスメイトの提案を聞いて麻里安はおずおずと友達の腕に触れた。こういうノリには慣れていない。こわばる麻里安の腕の隙間に、温かい腕が入り込む。おもわず、くすりと笑みをこぼす。
なんだか、ちょっと楽しいと思った。
◇
その日、麻里安ははじめて便箋の宛名の欄を埋めた。
『私の大事な名無しさん
先日はアドバイスありがとうございました。友達と行ってきましたよ、遊園地。あなたがまっすぐに背中を押してくれたから、迷いなく誘いに乗ることができました。正直、遊園地に行くまで怖かったし、友達と合流してからも最初はすごくすごく不安でした。でも、だんだん打ち解けてきて。教室ではお互いに何を考えてるかわからない、全然話の合わなそうな人だって思ってたのに、こんな風に一緒に遊べるんだって、すごく感動しちゃいました。女の子五人で遊園地を闊歩するなんて、いつも図書館で本ばっかり読んでる私の身には絶対に降りかからないイベントなんですから。
これも、あなたのおかげです。あなたと文通を始めなかったら、誰かと打ち解けてみたいなんて思えなかった。
できれば、直接お礼を言いたくて……それから、遊園地で買ってきたお土産も渡したくて。もし、よければ、なんですけど……。今度、お茶でもしませんか。あなたの名前が知りたいです』
最後の段落を何度も書き損じたせいで、いつも書く手紙よりも時間がかかってしまった。もう暗唱できるほど読み返して違和感がないかチェックした後、便箋をたたむ。
やっぱり、今のまま素性を知らずにいた方がいいんだろうか。互いの顔や名前を明かしてしまうことに一抹の迷いもある。けれど、思い切って先に進んでみたかった。
(怖い、けど、乗り越えたらきっと楽しいはずですよね)
すっかり手の馴染む一冊となった『夏の夜の夢』を図書館の本棚から引っ張りだすと、麻里安はページの隙間に手紙を挟んだ。落ち着かない足取りで図書館をでる。彼からの返事が届くのは、いつ頃になるだろう。
◇
「現在完了形、これはちゃんと使いこなせるようになりましょうね」
英語の先生が板書している。昼休みの直後である五限目の授業は、寝ている生徒が多くていつもより教室が静かだ。みんなお弁当を食べたおかげで満腹なんだろう。
窓の外から虫の鳴く声が聞こえた。夏のコオロギか、秋の鈴虫か。どっちだろう、と麻里安は頬杖をつく。暦の上ではもう秋に近づいている。近頃、虫の声や空に浮かぶ雲の形、机にできた傷跡なんかが、やたらと気になった。授業に集中できない。
(どうしましょう……)
どうしましょう、が口癖になりつつあった。何を? と聞かれたら困るけれど。どうにかしたいことがあるわけじゃない。どうにもならないことを抱えているわけでもない。それなのに、ぼんやりしていると自然に「どうしましょう……」が口をついて出そうになる。
(こんなに、そわそわすることないじゃないですか……)
英語の先生が、教壇で両手をぱん、と叩いた。
「はい! それではみなさんpracticeの2をやってみましょう! Let’s try」
麻里安はシャーペンを握る。英語の先生は、ずらりと並ぶ机の間を通り、教室を見回った。そして麻里安のすぐそばで立ち止まる。
「初瀬さん。今は英語の時間ですよ」
「あっ……」
麻里安は、机に出しっぱなしだった数学の教科書を机の中にしまった。
学校の図書室の古書整理は終わり、校内でも図書の貸し出しができるようになっていた。けれど麻里安は放課後になると、校内の図書室を横切って街の図書館へ向かう。
麻里安が彼にあてた手紙をいつもの場所に置いてから、もう三日がたった。そろそろ返事が来てもいい頃だ。やっぱり、名前を聞くのは失礼だっただろうか。お茶に誘うのも、まだ早かったのかもしれない。名無し同士の文通を続けていた方がよかっただろうか。
返事を待つうちに不安が押し寄せて、前回出した手紙の内容を悔いては一人で首を横に振った。
「今日こそ……」
麻里安は軽く息を吐いて呼吸を整えると、イギリス文学の棚へ向かう。図書館のすみにある、セピア色のその一角。
ひょい、と顔をのぞかせた瞬間、その場に足が釘付けになった。
(え……? 女の子……?)
イギリス文学の棚には、すらりと背の高いショートヘアーの女の子が佇んでいた。プリーツの入った制服のスカートからは細い足が伸びている。あろうことか、彼女はシェイクスピアの欄に指を伸ばしている。
(どうしてシェイクスピアなんですか、『夏の夜の夢』だけは手に取らないでください……)
彼女の一挙一動に見入ってしまう。その細い人差し指が『夏の夜の夢』に触れた。
棚に戻して、と心の中で叫んだ。けれど彼女は『夏の夜の夢』のページをめくる。本の隙間から、折りたたまれた便箋が滑り落ちた。
「あっ……」
それを見た麻里安は我慢できずにその場から走り去った。
図書館は公共施設だ。あの『夏の夜の夢』だって、麻里安と彼の二人だけのものじゃなく、誰もが読める本だった。そのくらいのことは当然、わかっていたはずなのに。
手紙のやりとりに舞い上がっていた。このまま素敵なことが素敵なままに続くんだと思っていた。もし関係が途絶えることがあるとすれば、それは自分か相手の手によるミスしかありえないと信じていた。それがまさかこんな、なんてことのない外的要因で崩れ去るなんて。ここは物語の中じゃなくて、やっぱり現実なんだ、と思った。
図書館の中を走る彼女のことを司書が睨みつける。けれど麻里安はお構いなしに、図書館の門を飛び出した。
本を一冊も借りずに図書館から出てきたのは初めてだ。麻里安はいつもより軽いカバンを肩に掛け直す。あの女の子に、自分が書いた最後の手紙を読まれていたら……と思うと顔から火が出そうだった。
もう、あの手紙のやりとりは終わりにしよう。図書館でたまたま出会った、顔も名前もわからない素敵な王子様。その姿のままで思い出に残すのも悪くない。
一人で帰路についていると、後ろから麻里安を呼ぶ声がした。
「初瀬さん? やっぱり初瀬さんだ」
このあいだ一緒に遊園地に行った友達だ。自転車に乗っている彼女は、すぐに麻里安の隣に並んだ。
「つぶあん平気? こしあんと間違って買っちゃったんだけど。いる?」
彼女から差し出された今川焼きを受け取って、麻里安はぎこちなく微笑む。
「ありがとうございます……せっかくだから、いただきますね」
図書館の王子様とは、もう会えないかもしれない。つぶあんがぎっしり詰まった今川焼きを頬張っていると、それでもいい、と思えた。
足元では虫が鳴いている。鈴虫だ。もう夏は終わった。麻里安は雲を見上げた。空は高く、赤々と燃えている。それはもうすっかり、秋の空だった。
◇
図書館に訪れた九十九伽奈は、読み慣れたサイエンスコーナーの棚を流し見て、イギリス文学の棚に向かった。
そして演劇の演目に選ばれた、シェイクスピアの『夏の夜の夢』を手に取る。そこには、数日前に自分が書いた手紙が未だ挟まったままになっていた。
「あの子は、もうこないのか」
頬をくすぐる短い毛先を耳にかける。それから、制服のスカートに落ちてきた埃を軽く払った。
「……どこかで、元気にしてるといいな」
本の隙間に隠した手紙を抜き取った。
『私も、あなたと会って話してみたいと思ってました。友達になれたら嬉しいです。 九十九伽奈』
その手紙は、そしてあの子の手元に渡らなかった。便箋を破ると、図書館のゴミ箱に捨てる。
図書館を出た九十九伽奈は、軽く伸びをした。外は澄んだ秋晴れだった。