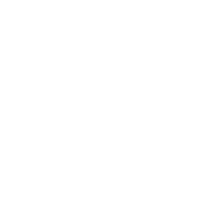第2話 東雲 龍「ホームランの女王」
見つめるのは、自分の打球の行方だけ。
龍は軽く腰を落とし、バットを握る。時速一四〇キロのストレート。バットの芯でボールを捉えた。鋭く打ち上がったボールは、天井に掲げられた「ホームラン」の看板にぶつかり、音割れしたラッパ演奏が室内に流れる。
「さすがだねえ」
おおらかに微笑むオーナーの前で、龍は再びバットを構えた。一本や二本のホームランで一喜一憂していられない。龍の目指す場所は、もっともっと先にある。
プロ野球で活躍している龍の兄は、試合中に年間四十本以上のホームランを打っていた。
(兄たちと比べることはない、私は私の野球をやるだけよ)
自分にそう言い聞かせても、脳裏に兄たちの姿がよぎる。
バッティングマシーンからボールが飛び出した。速さや球種はランダムに設定されている。龍は向かってくる球を黙々と打ち返した。
龍の通うバッティングセンターは駅から遠く離れたところにあった。自転車やバスでここに駆けつけるのは向上心のある野球部員ばかりだ。アミューズメントパークにあるバッティングセンターとは違って、精度の高いトレーニング用のマシーンが揃っている。
質素な壁には「先月のホームラン王」の名前が貼り出されていた。一位の座は、龍が独占し続けている。
「今月のホームラン王も龍ちゃんかな」
バッティングセンターのオーナーがそう言った時、隣のブースからホームランを祝うラッパの音が聞こえた。
二十歳前後の男の人だ。彼は軽く腰を回すと、休むことなく再びバットを構える。
「……ついに刺客が現れたね。念願のライバル出現だよ。どうする、龍ちゃん」
「今までと変わらないわ。私は私に必要なことをこなすだけよ」
フルスイングする龍のそばから、カンッ、と小気味良い音が聞こえる。連続ホームランにはならなかったものの、彼がバットを振るタイミングはばっちりだ。龍は隣のバッティングブースを一瞥する。
(どこの野球チームの人かしら)
彼は龍の方に見向きもせず、ただひたすらにバットを振っていた。野球一筋に見えるその横顔は、少し兄たちに似ていると思った。
◇
「ここで、東雲が打ちましたー! 兄弟揃って、今シーズンは絶好調ですね」
兄の顔が、テレビに大きく映し出される。小麦色に焼けた肌には玉のような汗が輝いていた。
外国から取り寄せたソファーにゆったり腰掛けている母が微笑む。
「うちのお兄ちゃんたちはみんなすごいわね。見た? ここだっ、っていうところで、しっかり打ってくれたわね」
「俺が社会人野球やってた頃よりずっとうまいな。子は親を越えていくんだなぁ」
母のとなりで、父が神妙に頷く。
龍には三人の兄がいる。そのうち二人はプロ野球選手として躍進中だ。末兄は大学野球で良い成績を残し、プロ入り確実だと言われている。
出塁する兄を見つめながら、私はどこまでいけるんだろうと思う。私のバッティングセンスはまだ、プロ野球に通じるようなレベルではないかもしれない。
テレビの野球中継で、たったいま兄が出塁したシーンが再編集されて流れる。スローモーションで見ると、ピッチャーが放つ投球がとてつもない角度で曲がっているのがよくわかる。私はあれを打ち返せるだろうか。
「あいつらは本物の天才だ」
そう褒め称える父の目には、プロ野球で活躍できる兄たちの姿しか映らない。
私がどれほど野球の道を追求しても、この人たちは喜ばないんだろうと思う。
龍は静かに席を外した。自宅の庭にあるバッティング練習場は大学野球で勝利を積み重ねている末兄の私物と化している。だからいつも通り、部屋で静かに筋トレをしてから、眠りにつくことにした。
バットを振り続けていると、自分が無になるようで気持ち良い。町外れにあるこのバッティングセンターは、一人で練習に没頭するのにもってこいだった。
(私が考えるべきなのは、ホームランを打つこと)
バットを構えると、隣からホームランを祝うラッパ音が流れた。また、あの彼だ。このくらいの球、打てて当たり前という顔で、打席に立ったまま次の球が来るのを待っている。
「今月のホームラン王はこいつじゃないか?」
「綺麗なスイングだな。思い切りがあるのがいいね」
バッティングセンターに集まる野球好きのおじさんたちが、彼の後ろに集まっている。そのギャラリーに惑わされることなく、彼は次々とボールを打ち、時折バットを持ったまま肩のストレッチをしていた。
龍は黙って彼に背を向ける。私は私の思うままに打つ。バットを強く握ると、マシーンから投げられたカーブを打ち返す。ホームランにはならなかったものの、飛距離のある打球だ。
バットを振り下ろすと、ホームランを量産する彼の方を振り返る。
「あ……」
ふいに、視線がぶつかった。彼は得意げにバットを肩にかつぎ、リラックスした表情で笑っていた。龍は唇を真一文字にきゅっと結び、目を逸らす。負けたくない、と思った。私は、ここにいる誰よりもうまくなりたい。
その男の人は、次の日も、また次の日もバッティングセンターに来ていた。いつも龍より早く来て、龍より遅くまで残っているらしい。オーナーによると「閉店ぎりぎりまで打ち続けている」という話だ。
壁には「今月のホームラン王」を記録するポスターが貼られている。ホームランを打つたびに名前の横に丸いシールが一つずつ増えていく。龍と彼の名前だけが突出して、一位と二位を争っていた。
ダルビッシュ・零。
龍は自分のとなりに並ぶ名前をつぶやいた。それはどう考えても、悪ふざけでつけたニックネームにしか思えない。
「東雲龍さん、って君だよね。かっこいい名前だ」
振り返ると、ダルビッシュ・零と名乗る男が立っていた。どこか飄々とした様子で、スポーツドリンクを飲んでいる。
「貴方、いくらなんでもこの名前はないんじゃないかしら?」
「でも、本名で登録したくなかったんだよ」
偽名を名乗る男はうつむいて、そわそわと自分のあごのあたりに触れていた。
「……貴方はどこの野球チームに入ってるの?」
「今はどこにも入ってないよ。ただ、打ちたくて。君は? チームの練習もあるでしょ?」
「練習のあとここによることにしてるの。一人で打ちたくて」
「そっか。俺と同じだね」
彼はどこか愛おしそうに目を細めて、バッティングブースへ戻って行った。
名前も素性も胡散臭い男だけれど、野球への想いに嘘はないようだ。龍はバッティングマシーンと対峙しながら、時折彼の様子を伺った。すぐそばでバットが風をきる音や、ボールをかっ飛ばす気配がするとつい振り返ってしまう。
(バッティングセンスがあるのは認めるわ。けど、私の方が……!)
龍がボールをバットの芯で綺麗に捉えると、彼がちらりと視線をよこす。龍は笑みを噛み殺しながら、涼しい顔で再びバットを構えた。
◇
「あーあ、あと一本だったのにな」
今月のホームラン王ランキングは、あの男と東雲龍が同率一位だった。ホームラン王を獲得した際の景品はいつも「バッティングセンターの無料回数券、一ヶ月分」と決まっている。龍はこの回数券を山ほどためているので、いつも無料でここを使っている。
「はい、回数券ね。じゃんけんで勝った方がもらうなり、山分けにするなり、二人で好きにしておくれ」
オーナーから回数券を受け取ると、彼はそれを半分にする。
「はい、君の分」
「いらないわ、私はもうたくさん持ってるから。貴方が全部受け取って頂戴」
野球チームに入っていない彼は、きっと練習場所に不自由しているのだろう。龍の申し出を受け、彼は嬉しそうに目を輝かせた。
「えっ、いいの? じゃあ、遠慮なくもらっちゃうね。お礼に飲み物でもごちそうするよ」
バッティングセンターの休憩所には、飲料水メーカーの広告が貼られたベンチが二つ並んでいた。彼は龍の斜め向かいに座る。
「君、上手だなー。俺がダントツでホームラン王になれると思ってたのに」
彼は悔しそうに喉を鳴らしながら缶ジュースを呷った。
「年下の女子相手なら、敵じゃないとでも思ってた?」
「とんでもない。君がこの先どんな選手になるか、楽しみだよ。君は、なんで野球始めたの?」
「最初に始めたのは、兄の影響かしら。貴方は?」
「ホームランに憧れたから」
「え?」
「いや、違うな。たぶん、クラスの可愛い女の子にモテたかったからだ。野球部にすごいかっこいいやつがいてさ。そいつが女子の人気を独占してたのよ。まあ、始めた理由なんて大したことないよな。ここまで続けてこられたのはまた、もっとちゃんとした理由が自分のなかにあるんだろうけど、うまく言えない」
続けてこられた理由。
龍も自分のなかにあるはずのそれをうまく説明できなかった。辞めたかったらいつでも辞めていい。親は女の私にはそこまで期待してないし、野球で成功する道なら兄たちがとっくに切り開いている。
龍は、彼から買ってもらったコーヒー牛乳にストローを刺した。
「貴方は野球チームに入ってないって言ってたけど、なぜ? プロを目指す気はないの?」
「それには、いろいろ事情があって。今は、ここのバッティングセンターで毎日打ってるだけだね。もっと近所のバッティングセンターに行こうかと思ってたけど、ここにしてよかったよ」
「ここは、本気で野球をやってる人しかこないところよ」
「ホームラン王の特典も無料回数券っていうのがいいよね。実用的だ。今回は折半することになった上に、俺が全部もらっちゃったけど」
「その分、これをご馳走になったから気にしないで」
「コーヒー牛乳一つじゃ、全然釣り合わないよ。貧乏なお兄さんでごめんなー」
彼はあごのあたりを軽くかいた。すると何か閃いたようで、悪戯っぽい笑みを浮かべる。
「そうだ。ちょっと賞金稼ぎに行かない?」
「……何を言ってるの?」
「この後時間ある? ちょっとそこまで付き合ってよ」
彼は目を輝かせながら立ち上がり、龍を誘った。
◇
彼に連れられて訪れたのは、数分歩いた場所にある別のバッティングセンターだった。ゲーム施設が併設されているせいで騒がしい。学生や、ストレス発散に来ているサラリーマンで賑わっている。
入り口から流れる陽気なJ-popに圧倒されていると、よく見知った顔を見つけた。
「あーあ、ベアマックスのキーホルダー欲しかったな〜…。すっごくレアなんだよ、非売品なんだから!」
「翼、元気だしなって。今日はたまたま調子でなかっただけだよ〜」
がっくりと肩を落とした翼が、友達と二人でバッティングセンターから出てきたところだった。まさかこんなところで貴女に会うなんて。友達とふらふら遊んでいるライバルの姿を見て、自然と眉間に力が入る。
「貴女……」
龍に声をかけられた翼は、怪訝そうに首をかしげた。
「ええっと……ああっ! そういえば、試合で……」
鈍い反応を見て、龍は奥歯を噛み締めた。貴女は、私の名前すら知らないの? 湧き出る苛立ちを押し殺しながら、冷静に挨拶を交わす。
「……また次の試合で会いましょう」
「うん! その時はよろしくね」
翼は再び、ベアマックス……とつぶやきながら去っていく。自分の存在より、そのベアマックスとやらの方が大事なのかと虫酸が走った。龍と翼は違う野球チームに入っていて、試合で何度も対決したことがある。男子に交じって硬式野球をする者同士で、互いに目立つ存在だった。
「……君にはいいライバルがいるんだな」
少し離れた場所から二人のやりとりを見ていた彼は、目を細めながら翼の背中を見送った。
「……ライバルとは言い難いわね。あの子は、私の名前すら覚えてないようだから」
険しい顔をしている龍を見て、彼が小さく吹き出す。笑わないでくれる? と静かな怒りをあらわにする龍から逃げるように、入り口のドアを開けた。
そのバッティングセンターはあちこちに風船が飾られ、一昔前のJ-popが流れている。
「華やかな場所ね。初めて来るわ……」
圧倒されている龍を導くように、彼が先頭をきって歩く。
「ここはホームラン打ったら結構豪華な景品がもらえるんだ。ホームラン二〇本打ったら遊園地のペアチケットだって。何か欲しいものある?」
壁に「ホームランの景品一覧」が貼り出されていた。ホームランを一本打てば、タオル。二本ならベアマックス。三本ならゲームセンターで使えるメダル……と、本数に応じてもらえる景品が豪華になっていくらしい。翼が言っていた「ベアマックス」を目の前にした龍は首をかしげた。それは今までに見たこともなければ聞いたこともない、不恰好なクマだった。翼がなぜこんなものを欲しがるのかわからない。けれど、とりあえずホームランを二本以上打つまでは帰らないと決めた。
「そうね……景品にはそこまで興味がないわ」
「そっ、そんな、俺のプレゼント計画が……」
彼は頭を抱えてうなだれたけれど、すぐに立ち上がり前歯を見せて笑った。
「じゃあ、ここにある中で一番豪華な景品取ってやるよ!」
◇
そのバッティングセンターから出る頃には、すっかり日が暮れていた。バス停を目指して西日に照らされる道を歩く。
「あー、打った打った。この、ホームランの感触がたまらないんだよなぁ。家帰ったらしっかりストレッチしないと!」
そう言って、首や肩を軽く回す。これでもかとホームランを打ち上げた龍は、巨大なアヒルのぬいぐるみを抱きかかえていた。
「これ、あげるわ」
龍はアヒルのぬいぐるみを彼の背に押し付ける。
「普通逆だろ!」
「ぬいぐるみは女の子だけのものじゃないのよ」
「そうかもしれないけど、今日は俺が君に何かお返しをあげる計画でーっ!」
「それにこのアヒル、なんだか貴方に似てるから」
「どんなところが?」
「にやっと笑ってるところ」
彼は、悪どそうな顔をしたぬいぐるみを見つめて眉をしかめる。
「それより、これ受け取ってくれないか。回数券のお礼だよ。どのみち俺は使わないから」
「……っ」
彼が財布から取り出した紙切れを見て、龍の表情が強張った。兄が出る試合のチケットだ。兄たちのことは関係ない。そのはずなのに、はるか先を走る兄たちの存在を感じるたび、自分の行く先が不安になる。追いつき追い越すだけでは足りない、私は兄と同じ舞台には立てないのだから。もっと先にいかないといけない、けれど、いつもどこかに兄の後ろ姿がちらついてしまう。
龍は、チケットを突き返した。
「私も、これはいらないわ。この試合のチケットなら、簡単に手に入るの。……私の兄が出る試合だから」
「君のお兄さん、プロ野球選手なんだ。それなら、招待席が取れるもんな」
「貴方は、野球観戦に興味ないの? 観に行けばいいじゃない」
「そうだなぁ……」
彼はどこか気まずそうに野球のチケットをカバンに戻す。その時、ふいにカバンから財布が落ちた。中に入っていた免許証やカードが散らばる。
カードを拾い集めるのを手伝った龍は、免許証に記載された名前に目をとめた。
「この名前は……」
どこかで聞いたことのある名前だった。首を傾げていると、ダルビッシュ・零と名乗っていた彼が微笑む。
「……俺、プロ野球選手だったんだ。そこまで有名じゃなかったけど、お兄ちゃんがプロ野球にいるなら、君も一応、一軍にいた選手の名前はよく知ってるのかな」
「プロ野球選手だった、ってどういうことかしら。今は……」
「今は自由契約になって、仕事を探してるところ。だからしばらく試合には出てないんだ。もしかしたら、次はないかもしれない」
横断歩道に差し掛かった。彼は立ち止まって、信号機を見上げる。バス停までの道のりはまだ遠い。点滅する信号機の光が彼の瞳に写りこむ。信号が赤に変わると、彼は少し俯いて目の前を通り過ぎていく車のタイヤをぼんやりと眺めた。
「野球だけやって生きていられたら最高だと思ってたけど、プロになってから、その一日一日が怖くて怖くて仕方ない」
「貴方は、ホームランを打った時の感触が忘れられなくて、打ちたくて打ちたくて仕方ないから、プロになった人なんだと思ってた。まだ打てるじゃない、ホームラン」
「……ホームラン、か」
信号が青に変わった。けれど、彼は歩道に佇んだまま動かない。龍は彼の背中にアヒルのぬいぐるみを投げつけた。彼は目を丸くして、足元に転がったぬいぐるみに目を落とす。
「私なら、打てる限り、野球をやめたりしない。誰がどうしようと。誰に何を言われようと。私には野球しかないって信じてる。だから、もっとたくさん打たないと、っていつも焦るの」
再び、信号が点滅しはじめた。その光を受けて、彼の瞳が揺れているように見えた。ふっ、と諦めたようにため息をつくと、彼は顔をあげる。
「そうだな。いつまでも逃げてちゃだめだな。どうせ、逃げられないんだから」
いくら足掻こうと野球から逃げられないのは、幸せな枷だと思いたい。逃げられないからこそ、進む道がはっきり見える。その呪いを信じて歩むだけでいい。それは少し恐ろしいことでもあるけれど、ありもしない逃げ道を探して遅れをとるよりずっといい。
「正直、まだ打ち足りない。でも、できれば次は試合中にかっとばしたいよ、観客席に向かってさ!」
彼は両手の拳を重ねると、赤信号に向かって素振りをした。
「私も、今ある記録を塗り替えてやりたいわ。プロになって、自分の道を切り開くの」
龍の鋭い目元に光が宿る。彼は穏やかに微笑むと、足元に落ちていたアヒルのぬいぐるみを拾い上げた。そしてぬいぐるみに向かってつぶやく。
「……契約先が決まらなくて、うじうじしてたんだけどさ……俺、独立リーグのテスト、受けるよ。だから、俺が試合に出る時は見に来てくれよな」
「もちろんよ」
信号が青に変わった。龍は彼を追い抜かし、早足で道路へ踏み出した。白と黒の横断歩道を軽やかに渡る。横断歩道の白を踏むと、出塁ベースを思い出してつい嬉しくなってしまう。
体の奥底には、バットに当たった打球の重さや振動、ベースの感触やグローブの革のにおいなんかが染み込んでいて、走り出すといつでも野球をしている時の興奮が血液の中に流れ出す。
ずっと野球で生きていたい、と思った。
どこまで行けるかまだわからない。だからこそ足を止めてはいけない。
横断歩道を渡り終えて振り返る。大きなアヒルのぬいぐるみを抱えた彼は、ちょうど横断歩道の白を踏み越えていた。